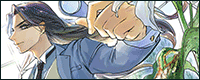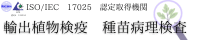コラム:植物病理学を学んだ企業研究者としての道 (サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 加野 彰人 氏)
はじめに
私は植物病理学ほど汎用性の高い学問は無いと考えています。詳細は後述しますが、植物病理学は多くの植物種、微生物種、ウイルス種を扱う点で特異な学問だからです。私自身、そこで学んだ経験が企業研究者として大いに活かされていると感じます。また、産業界においても、その汎用性や専門性に期待され、多くの共同研究が行われています。一般的に、アカデミアの研究がすぐに製品化につながることは多くありません。しかし、農薬の開発や病害抵抗性品種の開発には、植物病理学発の研究が深く関わっているケースが多々あります。このコラムでは、私の経歴を通じて植物病理学を企業研究者としてどう活かしているのか、植物病理学が産業界でどのように貢献しているのか、そして今後の展望について述べます。
植物病理学と私
私は学生時代に香川大学・植物病理学研究室(秋光和也教授)に所属し、企業との共同研究に参加しました。当時、香川大学で希少糖*1の農業利用に向けた研究を行っており、研究室の成果が製品化に向けた産学連携で進んでいる様子を目の当たりにし、キャリア形成に大きな影響を受けました。この経験がきっかけで、私はアカデミアではなく産業界から研究の発展や学術への貢献を目指すようになりました。当時行っていたのは遺伝子発現解析や遺伝子機能解析、タンパク質発現系を用いた酵素機能解析など、どちらかと言うと分子生物学に基づいた研究が中心であり、植物病理学に基づいた現場の研究とは距離がありましたが、共同研究を通して研究成果が社会実装される難しさと、現場での実用性が無ければ産業に利用されないという現実を学んだように思います。
さて、学生時代の植物病理学会との繋がりについて述べたいと思います。私はM1(編注:大学院修士課程1年)から全国大会、関西部会、植物感染生理談話会に欠かさず参加して発表を行っていたのですが、開催期間中はほぼ毎日飲み会に参加していた記憶があります。全国大会は通常三日間ありますが、懇親会の日は学生達で二次会、三次会、開催期間中のどこかで行われる大学のOB会でも二次会、三次会というように、連日連夜飲んでいたので、午前中のセッションへの参加が大変でした。関西部会では若手の会があり、そこで仲良くなったメンバーと飽きずに飲んでいましたが、その時に一緒に飲んでいたメンバーが大学や研究機関で活躍されている事も多く、今でも共同研究や情報交換をさせて頂いています。あまり胸を張って言える事ではないですが、飲み会で得た人脈や経験は意外と(?)今でも役に立っています。
学位を取得した後に入社したタキイ種苗株式会社では、病虫害研究グループの一員として病害抵抗性品種の育成に関わりました。植物病理学の専門性を期待されての入社でしたが、学生時代に扱った植物はイネとタバコ、病原菌はイネの白葉枯病菌とカンキツの黒腐病菌だけだったため、即戦力とは言えませんでした。しかし、同グループには伝統的に培われた各病害の培養方法や接種方法が確立されており、それらを学ぶことで、多くの病原菌を自ら単離する経験を積むことができました。これらの実学的な手法は、植物病理学会に所属する多くの公的機関、大学から導入されたものだと聞いています。このような現場に基づく研究の重要性を特に強く感じることができ、それらを就職後でも学ぶ機会があった事は、今の私の強みとなっているように思います。
私自身の植物病理学会との付き合い方も大きく変わり、特に農業試験場など、現場での研究をされている方との交流が増えました。時には病原菌のやり取りや接種、培養方法など多くの技術を教えて頂きました。また、学会での情報交換を通して、学術研究を起点とした製品開発ができないかと考えるようになりました。当時、私は罹病性遺伝子(Susceptibility gene)*2に着目しており、知見を品種育成に活かせないかと考え、積極的に関連する研究者との交流を深めました。
それがきっかけとなり、かつ私のキャリアにとって最も印象深い研究となったのは、農研機構の石川雅之氏、石橋和大氏と実施したtomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 抵抗性トマトの開発です。当時、新しいウイルス病として世界中で猛威を振るっていたToBRFVですが、具体的な解決方法はありませんでした。植物病理学会を通じて親交のあった両名と協力し、ToBRFVと同属であるtobacco mosaic virus (TMV) の罹病性遺伝子であるTOBAMOVIRUS MULTIPLICATION 1 (TOM1) の変異株をトマトで作製することでToBRFV抵抗性のトマト品種が開発できないかとの提案があり、この挑戦に取り組みました。結果的に、tom1破壊株のトマトはToBRFVの増殖を許容しない強力な抵抗性を示し、外観上も野生株に劣らないことが確認され、ToBRFV抵抗性品種の開発に繋がる技術として実証できました。
現場で培われた技術は重要な土台である一方で、TOM1の事例にあるように、大学や研究機関などのラボで行われる基礎研究も近代テクノロジーにより応用研究のステージに進む場面が増えているように思います。私自身が上手く研究から産業に結び付けられたと感じる場面の多くは、これら現場の知見、経験と新しいテクノロジーを融合させることが出来た時だと感じます。植物病理学が相対的に産業に貢献する事例が多いのは、学会内に現場研究から基礎研究までを網羅する様々な研究者が在籍されているからではないでしょうか。なお、先に述べたToBRFVについては、植物防疫所をはじめとする多くの方の努力により、日本への侵入が水際で防がれています。このように、我々の目に見えない所でも植物病理学に携わる方々が日本の農業を支えてくださっています。
私が考える企業研究者とアカデミアの違い
このコラムを読んで頂いている方には学生さんも多く、進路に迷われていると思います。また修士で卒業するか博士まで進むか迷われている方も多いと思いますが、私は博士号を取得し、企業に入社した経験から考えると圧倒的に博士号を取得しておく方が企業研究者として生きていく場合に有利だと感じています。一つには海外の研究者(アカデミア、企業研究者問わず)と連携する際に研究のプロか、そうではないかを肩書で判断される事があります。また海外では研究のプロジェクトをマネジメントするポジションには博士号が必須である事も多いですし、博士号というステータスは日本以上に重視されているように思います。日本でも博士を卒業したか、そうではないかはキャリア形成でも有利に働いていると思います。肩書そのものよりも、論文を執筆する経験を通してロジカルシンキングの能力や考察力が鍛えられることが大きいと感じます。また、日本においても研究職のマネジメント層は博士号を有している方が多く、私が耳にする範囲では、博士課程を過ごす中で自分のキャリアプランを見出しそれ向かって励んでいれば、博士号を取得した事が就職活動で不利になる事やキャリア形成が困難であるという事は無いと感じます。
アカデミアと企業研究者の最も大きな違いは何かというと、『研究の目的』では無いかと考えます。企業研究者である場合、研究の目標は社会に貢献する、もしくは産業価値のあるものを産み出す事にあります。アカデミアの場合は何かを知る事、解明する事が目的である場合が多いと思いますが、企業の場合は調査、解明を行った上で技術や製品価値のある物をアウトプットしなければならないため、単純な興味関心だけでは研究ができないという点では大きな違いがあると思います。ただ、企業目線でも価値の追求において知る事や解明する事は重要である一方、単独では基礎研究を掘り下げるのは難しいことも多いため、社会実装を見据えた上でも企業とアカデミアが共通の目標を持って連携していく事はこれからもとても重要だと思っています。
もしも企業研究者かアカデミアか迷われる場合、自身の価値観に従って進路を決められる方が良いと私は考えます。企業の場合は興味関心だけで研究はできませんが、製品になり、世の人々の手に取ってもらえるという点ではとても魅力的です。実際には研究成果が製品化される事は稀ですし、研究として成果が出ても、そこから製品まではかなり距離がある事も多いので、そこを結び付けていかなくてはならないとう点では苦労も多いのですが、それでも自分が関わった仕事が誰かの役に立っていると知ると嬉しくなります。そういった価値観を重視される方は企業で楽しく研究できるのではないでしょうか。
植物病理学と教育
以前から、植物病理学を学んだ多くの学生は農薬会社や種苗会社、農業試験場などでその専門性を活かして活躍してきました。近年では製薬会社や食品会社でも多くの卒業生が活躍しています。その要因の一つは、植物病理学が農業界において最も重要な学問分野の一つであることが挙げられるでしょう。人口増加に伴い農作物の安定的な収量を確保するには、病虫害の防除が重要な役割を果たします。新規の農薬開発や病虫害に耐性を持つ品種の開発は、これまでも大きな貢献をしてきました。その重要性は温暖化や天候不順といった気候変動によってますます増していると考えられます。媒介虫の生息分布の拡大による病害、例としてトマトの黄化葉巻病やカンキツのグリーニング病などをイメージするとその脅威を実感できると思います。
また、産業界において植物病理学を専攻した学生が活躍できるもう一つの理由として、植物と微生物の両面を学べる点があります。微生物と一口に言っても、糸状菌、細菌、ウイルス、さらにはウイルス媒介虫など幅広い植物病害虫を扱っています。このような広範な知識は、あらゆる企業の品質管理部門での活躍につながる潜在性を持っており、植物を原料とした食品や医薬分野への応用も可能です。植物病理学を専攻した学生は、自然と役に立つ知識を多く身につけているのではと思います。
産業界から見たこれからの植物病理学
私が学生であった頃、植物病理学の研究は通常、植物や病原体の研究、1対1の感染生理学、特定の病害に対する防除技術の開発が中心でした。しかし、近年ではよりマクロな視点で植物病理学が語られることが増えました。その背景には、SDGsに配慮した持続可能な農業が求められていることがあります。EUでは非常に厳しい農薬規制がかけられ、有機リン系*3やネオニコチノイド系*4の農薬使用が制限され、他の農薬についても1作型での散布回数が制限されています。このような規制の中で、様々な企業が新しい防除法の開発に取り組んでいます。例えば、エンドファイトを用いた病害抵抗性の付与や天敵を利用したウイルス媒介虫の防除などがあります。
また、育種では従来の交雑育種に加え、最先端のバイオテクノロジーが導入されており、ゲノム編集を用いた変異育種などがあります。
Downy Mildew Resistant 6 (DMR6) 遺伝子は植物のSARを制御するサリチル酸の不活化酵素をコードしており、この遺伝子が機能抑制された場合、多くの作物において耐病性を付与することが実証されています。最近では、イタリアで本遺伝子をゲノム編集により変異させ、べと病耐病性を持つワイン用ぶどうの栽培が始まっています(https://doi.org/10.1038/s41587-024-02478-8)。EUではゲノム編集作物は遺伝子組換え作物に分類されますが、規制が緩和されることを期待しての取り組みだと考えられます。
コラム執筆時の数週間前、理化学研究所からパターン認識受容体 (PRRs) をデザインし、それにより認識可能な病原体の範囲を拡張することや特定の病原体を認識するPRRsの発見が可能になるという内容の論文がScience誌に掲載されました (DOI: 10.1126/science.adx2508)。AIやゲノム編集技術を活用することで、抵抗性品種の改良が飛躍的に進展する可能性が示されています。
以上のように、アカデミアの研究から持続可能な農業を可能とする新しい技術が日々生まれています。この様な技術に目を向け、どの様に社会実装していくべきか、産業界にいる我々も引き続き考えていかなくてはならないと思います。
最後に
私は現在、食品会社であるサントリーグループの研究部門で研究を行っています。製品の中には植物と微生物の相互作用が味を決定づける要素となっている場合があります。例として、貴腐ワインの製造には菌類であるBotrytis cinereaの感染が不可欠ですし、”ナチュラル”と呼ばれるコーヒー豆の加工過程では、コーヒーの果肉が在来菌によって発酵することで独特の香味が生まれます。これらはよく知られた事例ですが、農産物の産地ごとの味にも在来菌の存在が関与している可能性があります。また、大手食品会社では持続可能な社会の実現に向けたさまざまな取り組みが行われています。具体例として、二酸化炭素排出量削減を目指した再生農業などが挙げられます。こうした持続可能な農法が広がると、病害防除の方法も大きく変化するでしょう。
最後に、植物病理学は産業界にとっても重要な分野です。抵抗性品種や防除技術は、多くの研究者が行ってきた研究の結晶であり、時代と共に変化する農業やテクノロジーのあり方の中で新たな技術が開発され続けていますが、病害との戦いは依然として続いています。この歩みが止まれば、産業界に大きな損失を招くでしょう。これからの若者が植物病理学に希望を抱き、卒業した人たちが多く産業界に貢献できる学会であることを願っています。
用語説明
*1. 希少糖:自然界での存在量が少ない単糖およびその誘導体のこと。存在量が少ないため、はたらきについては不明な点が多い。研究によって、様々な形で人間社会の役に立つ生理活性を持つものが含まれることが明らかになってきた。
*2. 罹病性遺伝子(Susceptibility gene):病原体が感染した宿主(病原体が感染する相手の生物のこと)が病徴を発する程度を強めるのに必要な宿主側の遺伝子のこと。病原体は多くの場合、罹病性遺伝子の産物を利用して感染していると考えられるため、罹病性遺伝子を欠失した宿主に病原体が感染した際には病徴は弱まり、場合によっては感染が成立しない。感受性遺伝子と呼ばれることもある。
*3. 有機リン系農薬:化学式にリン(P)を含み、Pを元に硫黄(S)や酸素(O)が結合する殺虫剤。昆虫などの神経系のアセチルコリンエステラーゼのはたらきを阻害することで作用する。水質汚染や人間など他の動物に対する有害性が問題となっている。
*4. ネオニコチノイド系農薬:ニコチンに似た化合物を有効成分とする殺虫剤。有機リン系農薬と同様に神経系のアセチルコリンエステラーゼのはたらきを阻害することで作用するが、有機リン系農薬より昆虫に対する特異性が高いため、人間など他の動物に対する有害性は低いとされる。しかしながら、花粉媒介昆虫であるミツバチ等に対する有害性が問題とされている。
プロフィール(掲載時現在)

加野 彰人(農学博士)
現職:サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 研究部 主幹研究員
経歴
・愛媛大学連合農学研究科博士課程(2013年卒業)
・日本学術振興会特別研究員DC1(2010年-2013年)
・タキイ種苗株式会社・病虫害研究グループ(2013年-2023年)
・Takii France S. A. S. (2023年-2024年)
・現職(2024年より)