
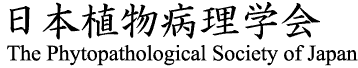
| 【平成14年度会費納入のお願い】 【学会員の他学会における受賞】 道家紀志氏および露無慎二氏は,この度下記の賞をめでたく受賞されることが決定致しましたのでご紹介いたします. 1.道家紀志氏(名古屋大学教授) 賞の名称:米国植物病理学会賞(Fellow for the American Phytopathological Society) 受賞の対象:疫病菌に対する宿主植物の過敏感型抵抗性誘導機構を研究し,その発現誘導シグナル反応としてのオキシダテイブバースト現象の発見とそのパイオニア的研究の展開により,植物の感染防御応答の生化学・分子生物学的機構研究に新時代を切り開いた.また,ジャガイモ疫病菌のレース特異的サプレッサー因子の発見とその作用機構の解明から,レース−品種特異性決定機構の理解への一局面を拓いた.さらに,全身的オキシダテイブバースト現象の発見とそのシグナル伝達機構の解明を通して,全身獲得抵抗性誘導機構の解明に新局面を切り開いた.何れも植物の感染防御機構の解明における重要な発見で,そのパイオニア的研究の展開が学術研究の方向に大きな影響を与え,植物の病害抵抗性に関する基礎および応用的研究の発展に多大な貢献をした. 2.露無慎二氏(静岡大学教授) 賞の名称:米国微生物学会賞(Fellow for American Academy of Microbiology) 受賞の対象:植物病原細菌の発病・抵抗性誘導因子の生産制御および作用機構について「基礎分解産物による誘導機構」,「自己代謝産物抑制」,「植物成分による超誘導機構」などの重要な発見を行い,顕著な科学的成果をあげた.また,レポーターファージを用いた細菌検出法を開発するなど,微生物の応用分野の発展にも多大な貢献をした. (松山宣明) 【今後の学会活動予定】 【今後の関連学会情報】 【今後の関連国際学会情報】 【学会活動状況】 1. 研究会開催報告 (1)感染生理談話会 平成13年度植物感染生理談話会は,平成13年7月23日より25日に,山梨県富士吉田市人材開発センターにおいて,「生物間の相互認識とシグナル伝達」のテーマで開催された.講演としては,岩田道顕氏(明治製菓薬品総合研究所)「化学物質による植物の自己防御機構の活性化」,長谷 修氏(東北大学農学部)「リゾバクテリアによって誘導される全身誘導抵抗性(ISR)のメカニズム」, 横山 正氏(東京農工大学農学部)「根粒菌Nod factorがダイズ細胞に誘起する初期シグナル応 答機構 −共生シグナルにおけるカルシウムの役割−」,蔡 晃植氏(奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科)「イネによる植物病原細菌Pseudomonas avenaeの認識と抵抗性反応誘導機構」,澤田宏之氏(農林水産省 農業環境技術研究所)「Pseudomonas syringae群細菌におけるファゼオロトキシン産生遺伝子群の水平移動と病原性」,大島一里氏(佐賀大学農学部) 「カブモザイクウイルスの分子進化的研究:宿主適応,リコンビネーションそして地理的分布がウイルス拡散に及ぼす影響」,夏秋知英氏(宇都宮大学農学部)「植物の二本鎖RNA:RNA植物ウイルスの祖先型か退行進化の結末か?」,有江 力(東京農工大学農学部)「子のう菌の交配型遺伝子と病原性進化に関する考察」,児玉基一朗氏(鳥取大学農学部)「Alternaria alternata病原菌群における宿主特異的毒素生産と病原性の分子遺伝」,鎌倉高志氏(理化学研究所微生物制御研究室)「いもち病菌の付着器形成・誘導に関わる遺伝子」の10題に加えて,浅見忠男氏(理化学研究所植物機能研究室)「植物生長におけるブラシノステロイドの多機能性」,深津武馬氏(生命工学工業技術研究所生物化学工学研究室)「昆虫の内部共生微生物の機能・進化・起源」,柴田大輔氏(かずさDNA研究所)「ゲノム農学−新しい植物バイオテクノロジーを目指して−」の3題の興味深い特別講演をしていただいた. 参加者も95名を数え,活発な議論がなされた.初めての試みとして行ったポスター発表にも,大学院生を中心に21題の発表がなされ,ポスター説明の部およびイブニングディスカションにおいて,ワイン片手に活発な討論・交流がなされたことは主催者側の予想を超えるものであった.(寺岡 徹)
(2) 第21回植物細菌病談話会 第21回植物細菌病談話会は帯広市十勝プラザで平成13年9月5日(講演会)〜6日(現地見学会)の日程で開催され,全国から101人が参加した.プログラムは3部構成であり,第1部は北海道で発生する細菌病の概要とタマネギりん片腐敗病およびブロッコリー花蕾腐敗病の発生生態・防除,第2部はジャガイモそうか病菌に焦点を絞り,Streptomyces属菌の分類の現状と問題点,産生毒素,モノクローナル抗体の作成および土壌からの検出・定量法,第3部は検出技術に関する講演でジャガイモ黒あし病菌,Erwinia chrysanthemiの検出法,発光ファージ゙を利用した細菌の検出,の話題提供のもとに活発な討議がなされた. 講演要旨集には,この他に「最近報告された新しい細菌病(3)」,「植物病原細菌に関する資料集」も掲載されており,また今回ISSN 1346-5767が付与された.26日の現地見学会では,音更町でイネ葉しょう褐変病およびブロッコリー花蕾腐敗病を,道立十勝農試でジャガイモそうか病および黒あし病を観察し,鹿追町では野菜複合大規模畑作圃場を見学した.午後から,十勝ワインを傾けながらバーベキューを楽しみ,好天にも恵まれて盛会のうちに終了した.次期開催地は宮崎大学と決まった.(宮島邦之) 2. 植物病原菌類談話会の設立にあたって 平成9年10月,島根関西部会の夜,生物8界説における卵菌類の扱いが話題となり,本談話会設立の話が持ち上がりました.翌10年の北海道大会で有志数人にお集まり頂き,さらに11年の新潟大会でより広範な方々のご意見を伺い,下記のような趣意書のもと,12年の岡山大会から開催にこぎ着けることが出来ました.今後は,本学会員諸氏のご意見を頂きながら,分類研究者のネットワーク作りや最新分類情報・同定手法に関する相談コーナーを充実していきたいと考えています.設立にあたり,多くの方々にご支援を頂きましたこと,この場をお借りして厚く御礼申し上げます. <談話会設立の趣旨> 植物病害の中で糸状菌病は最も重要な位置を占め,その病原は多岐にわたります.病原各菌群の分類体系は日々発展しており,最新情報や世界的動向は一部の専門家でないと分かりにくい状況になりつつあります.一方,分子生物学的手法による系統進化に関する研究も急速に進んでおり,従来の分類学は数々の転換を余儀なくされております.また,作物や栽培様式の多様化や生産の高度な専門化に伴い,農業の現場にいる研究・指導者にとって日々の仕事を行う上で,病原菌の見分け方の実践的知識がますます必要となってきております.しかしながら,現在の研究の環境では,個人の努力で多様な菌群の分類体系や同定技術を修得しつつ,自らの研究課題を遂行していくには限界があります. そこで,糸状菌病,特に分類学(及びそれに関連した生態学的側面)を含む糸状菌の取り扱い方に興味をお持ちの方々にお集まりいただき,お互いにそれぞれが取り扱っている菌との付き合い方や悩みを気軽に話し合う場として「植物病原菌類談話会」を企画いたしましたので,ご案内致します. (世話人代表 佐藤幸生(富山県立大学短期大学部)) 【書 評】 瓜谷郁三編著:「ストレスの植物生化学・分子生物学 熱帯性イモ類とその周辺」,A4判,308pp. 発行:学会出版センター,¥5,800 本書は,本学会永年会員でサツマイモ黒斑病における苦み物質,イポメアマロン・ファイトアレキシンの発見で著名な名古屋大学名誉教授瓜谷郁三氏が編著されたもので,先生が研究生命を傾けられてこられた熱帯性イモ類(サツマイモ,キャッサバ,タロイモなど)に焦点を当てながら,植物の物理的傷害,病害,虫害,有毒成分傷害,低温傷害などの各種ストレスに対して示す諸現象について,物質生化学,動的生化学,分子遺伝学,分子細胞学の分野および関連応用分野において積み上げられてこられた成果を集大成し編集されたものである.本書は全20章からなり,編著者を筆頭に編著者の薫陶を受けた各研究分野の専門家17名が執筆されている. 特に,戦後から今日までの50年間にわたる熱帯性イモ類の塊根組織を研究材料とした病傷害ストレスを中心とし,呼吸,細胞オルガネラ,貯蔵タンパク質,ポリフェノール類,クマリン類,リグニン,ファイトアレキシン,エチレンなどに関する代謝とその変動,病傷害に対する応答と情報伝達,ストレス応答と遺伝子発現,ストレス応答と細胞内・細胞間物質輸送など,ストレス分子植物科学の発展のプロセスと学問的現状が,相互の関連を含めて理解しやすく総合的にまとめられている.その意味で,植物の病傷害ストレス科学を網羅的に理解ができるばかりでなく,未来を背負う若い研究者にとって,学問がどのように進められていくものか,示唆に富むところが大きい. 本書は21世紀における分子植物科学および農業,園芸,植物保護および食品・栄養の科学などの発展への貢献を視野にいれつつ,また,21世紀の進行とともに顕在化しつつある世界的規模の食糧問題の解決に役立つことを願って編著された成書で,編著者の研究生命を支えてきた奥深い研究者魂をうかがい知ることができる.(道家紀志) 【学会ニュース編集委員会コーナー】 編集後記 |