
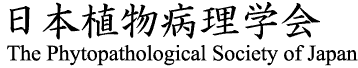
| 【名誉会員・永年会員・日本農学賞受賞者の略歴とお話】 名誉会員 浅田泰次 昭和3年6月19日大津市に出生。昭和26年3月京都大学農学部農林生物学科卒業。同年5月京都大学農学部助手。昭和31年4月愛媛大学農学部助教授。昭和37年3月農学博士 (秋落稲のごま葉枯病罹病性に関する研究) 。昭和40年12月愛媛大学農学部教授。 昭和46年日本植物病理学会評議員 (22ヵ年) 。昭和50年2月愛媛大学学生部長併任 (5ヵ年) 。同年4月日本植物病理学会賞受賞 (病態植物組織におけるリグニンの生合成に関する研究) 。昭和52年1月最新植物病理学概論 (平井・西村・井上共著) 出版。 昭和54 〜 56年日本インドネシア農学学術交流事業団長 (3ヵ年) 。昭和56年5月日米科学協カセミナー, 植物感染の生理生化学的基礎 (ミネソタ州ブレイナード) 主催。昭和56年11月最新植物病理学概論改訂版出版。昭和57年6月PLANTINFECTION出版。 昭和58年4月AGRO-ECOLOGICAL SURVEY, INDONESIA 出版。昭和60年3月愛媛大学農学部長併任 (3ヵ年) 。昭和63年3月愛媛大学長 (3ヵ年) 。平成2年1月タイ王国メチョー大学名誉博士。平成3年2月『最新植物病理学概論』第2次改訂版 (井上・後藤・久能共著)出版。 同年3月愛媛大学名誉教授。同年10月宮中園遊会に招待される。平成4年5月日本植物病理学会長 (会長講演: 生体防御システムー病態植物におけるリグニンの生成とその誘導機作一) 。平成5年4月学校法人松山大学教授。同年5月中国西南農業大学名誉教授, 文部省大学設置学校法人審議会専門委員 (5ヵ年) 。 平成7年4月放送大学客員教授・愛媛学習センター所長 (4ヵ年) 。同年7月松山ロータリークラブ会長 (1ヵ年) 。平成9年3月『最新植物病理学概論』第2次改訂版5版3回出版以後廃刊, 合計出版部数4万6千部。著書論文等104編, 国際会議講演18回, 海外出張29回, 趣味, ゴルフ (ハンデ20) , 囲碁 (2段) , 俳句, 音楽。 家族, 妻 (医学博士, 耳鼻咽喉科開業医) , 娘 (王立ロンドン音楽院修士, 愛媛大学教育学部非常勤講師) , 婿 (医学博士, 愛媛大学医学部助教授) , 孫3人。 “杉木立しぐるるばかり武蔵野陵" 名誉会員 梶原敏宏 昭和4年3月10日大分県日田郡東有田村 (現日田市) で出生, 旧制日田中から陸士へ。終戦のため宮崎農専に転入学, さらに九州大学農学部に入学し昭和27年卒業, 直ちに農林省に入省, 農業技術研究所病理昆虫部に配属され, 岩田吉人室長のもとで, 麦類雲形病菌の系統について研究。この研究によって学位を取得 (昭和36年) 。 引き続いて麦類黄さび病のraceに関する研究を開始。この研究のため, 西ドイツ (当時) 連邦農林生物研究所 (BBA) に昭和37年8月より1年間留学 (フンボルト奨学金による) した。昭和41年農技研糸状菌病第一研究室長に就任, べと病菌さび病菌など純寄生菌の感染機作, とくに吸器周辺の微細構造について研究を進めた。 この間昭和48年より2年間, インドネシア中央食用作物研究所 (ボゴール) において, 国際協力事業団の専門家として研究協力に従事した。 その後, 熱帯農業研究センター研究第1部長, 農技研病理科長, 農業研究センター総合研究官, 次長を経て, 熱帯農業研究センター所長を最後に, 昭和63年10月退官, 平成元年より(有)国際農林業搦力協会技術参与, 平成3 〜 9年5月まで(代)日本植物防疫協会理事長, 9年5月から会長に就任し現在に至る。 また平成2年より6年間, ペルーのリマにある国際ばれいしょセンターの理事を務めた。 学会の役員歴は長い部類に属すると思う。庶務幹事 (昭33 〜 35) を皮切りに, 幹事長を務め, 評議員は昭和45年から平成8年まで13期26年におよぶ。また病名目録の初版1, 2, 3巻の編集幹事, さらに病名調査委員長 (昭42 〜 50) , 第5回国際植物病理学会議の京都での開催には事務局長を務め, 平成元 〜 3年には副会長, 会長を歴任した。 学会の運営に携わった年数は38年におよび, 学会創立80周年を記念して功労賞をいただいたが, その背景については, 学会報61 (4) 学会ニュース2号で紹介させていただいた。また, 学会に対する要望は, 永年会員になられた尾添茂氏の意見と全く同じである (学会ニュース6号, 平成9年) ので, それらをご覧いただければ幸いである。 (追記: 梶原敏宏氏は「べと病菌の感染機構に関する研究」に対して昭和55年度日本植物病理学会賞, および「ムギ類・イネ科牧草の雲形病菌並びに黄さび病菌の系統分類の解析等, 試験研究行政の貢献」に対して平成11年春の勲三等瑞宝章を受賞されました。) 名誉会員 小林享夫 1929年1月16日, 東京府荏原村に生まれる。山水中学 (現桐朋高校) を経て東京物理学校農業理科学科 (現東京理科大学) 卒業。1950年3月農林省林業試験場保護部樹病研究室に採用, 1968年3月同樹病研究室長, 1988年同樹病科長, 1988年10月組織改編により森林総合研究所森林微生物科長, 1989年3月農林水産省定年退職, 同年4月(株)林業科学技術振興所主任研究員, 1994年4月全国森林病虫獣害防除協会技術顧問 (森林防疫誌編集) , 1995年4月東京農業大学農学部国際農業開発学科教授, 1999年3月同大学定年退職。 1977年以降熱帯農業センター派遣研究員, 国際協カ事業団短期専門家, あるいは相手国招聰研究員としてフィリピン (4回延べ8ヵ月) , インドネシア (8回延べ12ヵ月) , パラグアイ (1回2ヵ月) , 中国黒竜江省 (1回2ヵ月) , 韓国 (1回15日) における農林業の研究・技術協力に力を尽くす。また調査団長・調査団員としてタイ・ミャンマー・マレーシア (サラワク) ・ベトナムにおける農林業の現状を調査する。 1969年3月農学博士 (北海道大学, 第718号, 日本産胴枯病菌科菌類の分類学的研究) , 1972年4月日本植物病理学会賞受賞 (日本産ディアポルテ菌科菌類の分類学的研究) , 1997年5月日本菌学会賞 (日本および熱帯・亜熱帯地域における樹木病原菌類の分類・同定に関する研究) 。本学会においては学会報編集委員 (1974 〜 1988年) , 病名調査委員長 (1985 〜 1989年) , 日本有用植物病名目録4, 5巻編集委員長 (1980 〜 1984年) , 評議員 (1986 〜 1989年) , のほか庶務幹事1期 (2年) を務める。この間非常勤講師として樹病学 (東京教育大学農学部: 1968 〜 1977年, 東京大学大学院農学系: 1978 〜 1983年, 千葉大学園芸学部: 1983 〜 1991年) , 植物病原菌学 (宇都宮大学農学部: 1993 〜 1999年) の講義を行う。 研究歴: (1) スギほか針葉樹の赤枯病 (1950 〜 1986年, 論文6編) , (2) マツ材中の菌類とマツノザイセンチュウあるいはニトベキバチとの相互関係 (1965 〜 1980年, 論文6編) , (3) 針葉樹漏脂性病害の病原学的研究 (1970 〜 1990年, 論文14編) , (4) 樹木病原菌の分類・同定 (1955年 〜, 論文46編) , (5) 熱帯・亜熱帯の樹病・病原菌の調査と分類・同定 (1977年〜, 論文18編) 。 名誉会員 山田昌雄 本籍は福井市。昭和3年10月15日京都市に生まれ3才の時東京に移った。都立高校尋常科から高等科に進んだが, 2年上に吉田孝二氏, 1年上に寺中理明氏がいた。昭和24年東京大学農学部農学科に入学, 明日山秀文教授のもとで日本のコムギ赤, 黒さび病菌レースの分布を調べた。27年農林省に入り東北農業試験場盛岡試験地でさびの仕事を続けた。35年農業技術研究所に移りいもち病菌レースの共同研究に参加した。これがいもちとの縁の始まりで, その後北陸農業試験場病1研, 農事試験場病1研, 馨業技術研究所糸状菌病2研の各研究室長としていもち病菌レースの判別と生態を研究した。 それ以降北陸農試環境部長, 農業環境技術研究所環境生物部長を務め, 平成元年に退官しJTの顧問として微生物農薬の開発を手伝っている。 昭和36年, コムギ赤さび病菌のレースとその生成要因の研究で学位をいただき, 以降はいもち病菌レースの判別と生態の研究で, 55年に日本植物病理学会賞, 60年に農林省職員功績賞, 平成5年に日本農学賞, 読売農学賞をいただいた。 このように私の研究歴はさびといもちのレースだけである。レースの仕事は数をこなさねば何も言えないから, 明けても暮れても菌を分離し培養し接種し, レースを判別することに終始した。慣れてくると接種機械になったような気がしてくる。仕事だから仕方ないと頑張っている中に, 単調な結果の示すものが読めてくる。長年のレースの研究で, 韓国における統一系晶種の罹病化が最も記憶に残っている。微生物除草剤の仕事で, あらゆる植物の病気を見るようになり, 植物病理学の面白さを改めて知った。10年で1剤を得ただけであるが, 日本の微生物除草剤の第1号, 細菌を用いた剤では世界最初である。 微生物農薬は問題点も多いが, IPMの重要な構成要素になるものと夢を描いている。学会に対して胸を張れるほどの貢献はない。昭和41 〜 42年に幹事長, 51 〜 平成5年に評議員のほか, いくつか委員も務めた。平成元 〜 5年には学会報総目次編集委員長を仰せつかり, 多くの委員に助けていただいて何とか総目次を作り上げたが, 果たして常用されているのかどうか。新潟学会で名誉会員にしていただいて, 学会から卒業証書をいただいたつもりになったが, 後にこれは成人証書だと思うようになった。今後も学会というより学界にお役に立っていきたいものである。 永年会員 下山守人 大正7年7月4日青森県十和田湖町に生まれる。昭和15年3月盛岡高等農林学校農学科卒。同校では植物病理学専攻生として富樫浩吾教授・村山大記講師からご指導をいただいた。同校研究生の同年12月現地中国に応召。中国各地を転戦。17年北京自動車教育隊 (予備士官学校) 見習い士官で助教のとき, 飯塚慶久氏が甲種幹部侯補生として入隊してきたのは奇遇だった。4年半にわたる戦地勤務後の20年8月帰還。21年11月青森青年師範学校講師。24年学制改革により弘前大学分校となる。同年10月から25年3月まで東京大学植物病理学研究室に内地研究。 弘前大学を辞して28年4月から31年3月まで東大植物病理学研究生。明日山秀文教授・輿良清助教授からご指導をいただいた。この3年間は専ら明日山先生の「コムギ赤さび病菌のレースに関する研究」について, 接種試験などのお手伝いをした。 31年4月から49年3月まで長野県農業試験場勤務。主として農林省指定試験「いもち病菌のレースに関する共同研究」を担当した。49年4月明治大学農学部教授となり, 平成元年3月に退職したが, その後6年3月まで大学院非常勤講師を務めた。この間, 昭和54年8月から10月までカナダ・アルバータ大学に短期外地研究。比留木忠治教授から植物マイコプラズマ病についてご指導をいただいた。55年12月にはそれぞれ10日間ぐらいSAEDA (海外農業教育研究協会) から派遣された茨大柏原孝夫教授を団長とする調査団, 東大・名大・東農大教授とともにバングラデシュ・ネパールの農業関係試験研究機関・大学などを視察。進歩発展のための提案を行った。 私は80歳の今, 過ぎし日を顧みて, ただ50年間日本植物病理学会員であったというだけで, 学会に対する貢献もなく (評議員1期) , みるべき研究業績もなかったことを恥じる思いである。 永年会員 松濤美文 大正12年5月7日広島県豊田郡佐江崎村で出生。昭和18年12月学徒出陣で, 山口県柳井の陸軍船舶工兵隊に入営。その日早速古年兵に馬は一匹200円もかかるがお前らは1銭5厘 (当時の召集令状の切手代) で来ると気合をいれられた。のち愛媛県の豊浜の同幹部候補生部隊で1年間訓練を受けたのち, 小樽, 新潟, 男鹿の各港の船舶司令部支所を転々として, 終戦を迎え復学。昭和22年3月東京農林専門学校卒, 同年4月農事試験場病理部 (西ヶ原) ウイルス病研究室勤務。昭和29年横浜植物防疫所に, 同32年神戸植物防疫所に転勤する。昭和37年養子縁組により加藤より松濤姓になる。同38年横浜植物防疫所に再転勤。 昭和55年農学博士 (検疫中に発見された植物ウイルスの同定ならびに診断に関する研究) 東京大学。昭和56年4月農水省を退職。同年北興化学工業に就職, 開発部, 研究所を経て, 同社を退職し現在に至る。横浜植物防疫所勤務中は主として, 調査研究部, 業務部に所属し隔離検疫中のウイルスの検出ならびに, その方法の研究をした。ほとんどの輸入植物は港, 空港で検査を受け, 病害虫が寄生していなければ, その場で輸入出来るが, 果樹類, サツマイモ, ジャガイモ等はその場では発見出来ない重要病害虫が寄生している可能性があるため植物防疫法で, 隔離圃場で栽培し検疫を受けた健全な植物のみが輸入出来るように規定されている。 この検疫は各植物防疫所の隔離圃場で担当し, 私は神奈川県大和市にある圃場で, この検疫に従事した。昭和41年ソ連から輸入された隔離検疫中のジャガイモから, Aウイルスを検出した。残念ながら本ウイルスは同43年国内産のジャガイモからも発見された。昭和42年新潟県下の指定隔離圃場で栽培中のオランダ産チューリップから我が国未発生のタバコネクロシスウイルスを検出した。昭和47年大和隔離圃場で栽培中のダリアの無病徴の葉汁をタバコに接種したところ, モザイク病徴が発生した。同定の結果タバコ条斑ウイルスと判明した。本ウイルスは寄主範囲が広く, 21科87種の植物に感染するとの報告もある。 また許可を受け, 我が国には未発生のジャガイモスピンドルチューバウイロイドの診断方法を検討した。この結果, 検定植物より電気泳動法が異なる系統の同ウイロイドをも検出されることが確認された。 日本農学賞受賞者 後藤正夫 昭和6年3月1日静岡県生まれ。昭和26年静岡農林専門学校農学科卒業。昭和26年静岡大学助手雇員, 昭和28年同助手, 昭和40年同助教授, 昭和48年同教授, 平成6年同定年退官, 名誉教授。平成6年MOA自然農法大学校講師・技術顧問。平成10年(株)微生物応用技術研究所技術顧問, 現在に至る。昭和36年農学博士。昭和46年日本植物病理学会賞受賞。昭和48年 〜 平成8年病名調査委員会委員, 昭和51年 〜 平成8年評議員, 平成4年関西部会長 (1年) 。第2回, 第3回, 第4回国際植物病理学会議組織委員会細菌病部会委員, 第5回国際植物病理学会議組織委員会プログラム委員長。平成4年日本学術会議植物防疫研究連絡委員会委員 (2年) 。 平成5年国際微生物連合細菌分類委員会委員・同アジア地区連絡委員 (2年) 。平成11年日本農学賞, 読売農学賞受賞: 受賞論文「植物細菌病の病原学的研究」。 私は40余年にわたって植物病原細菌の特性を, 分類学, 生理学および生態学の視点から研究してきました。特に, 日本産植物病原細菌の分類に関する研究, イネ細菌病の研究, カンキツかいよう病の研究, 軟腐病菌の血清学的研究, 植物病原細菌の新機能に関する研究, の5課題は代表的な研究であります。またこれらの研究結果を主な柱にして, 新たに植物細菌病学を体系化し, 新植物細菌病学 (ソフトサイエンス社, 1981), Fundamentals of Bacterial Plant Pathology (Academic Press, Inc., 1992) などを著しました。今回, 日本植物病理学会から御推薦を賜り, 日本農学賞を受賞できましたことは身に余る光栄でございます。 お世話になりました松山宣明前会長をはじめ関係各位, ならびに今日まで長年にわたり御指導ご鞭撻をいただいた多くの先生方に謹んで厚くお礼申し上げます。大学の研究室から農業の現場に移って5年, 病害発生の多様な側面に, 目から鱗が落ちるような思いを繰り返す, 新鮮な日々を送っております。 【平成10年12月 〜 平成11年5月め学会活動状況】 1.大会開催報告 平成11年度日本植物病理学会大会は平成11年4月2日から4日にかけて新潟大学教養校舎を会場として開催された。大会参加者は700余名にのぼり, 講演題数388題, 懇親会参加者は405名であった。大会初日は生憎の雨となり, 参加者を震え上がらせてしまったが, 2日目から幸い天気も回復し盛会のうち無事終了することができた。 講演題数が札幌大会並みとなると考え, 5会場とした。新潟大学のような小さな世帯では1会場増とて大変苦労するところであった。今の我が国の姿を考え,「普段着の学会」を心がけたところであるが, その為会員のみなさまにはご迷惑をおかけしたのではないかと内心忸怩たるものがある。 本大会は北関東ブロックの会員によって運営され, 新潟県・新潟市・大会賛助会社などの財政的支援によって実現した。記して感謝の意を表したい。(小島誠) 2. 研究会開催報告 (1) 第2回植物病害生態研究会 第2回植物病害生態研究会は「植物病原菌の分子生態学, 分子マーカーによりブラックボックスを探る」をテーマに平成11年4月1日(木), JR新潟駅前の第一総合生協会館で開催された。参加者は115人 (大学23, 都道府県39, 国27, 学生12, その他15) と予想を大きく上回り, 会場からあふれるほどの熱気であった。研究会では「イネいもち病は, 何故, 今も問題なのか, その生態のブラックボックス」原澤良栄氏 (新潟農総研) ,「進化生物学における分子マーカーの原理と利用法 (多様な手法とその特徴)」綿野泰行氏 (金沢大理),「ピシウム属菌の生態の多様性と分子マーカーによる解析の可能性」東條元昭氏 (大阪府大農) の3題の講演がなされ, 総合討論でも活発な議論がなされた。 綿野氏の講演資料に対する要望が高いため, E-mail連絡者のみ当日のOHP原稿ファイルを配布する。連絡先は東北農試石黒 (ishiguro@tnaes.affrc.go.jp)。PowerpointあるいはPersuasionの形式で配布できる。第3回は平成12年4月5日に岡山大学で病害のIPM等をテーマに開催予定である。(石黒潔) (2) 第6回バイオコントロール研究会 第6回バイオコントロール研究会は, 平成11年4月5日, 新潟大学教養校舎において, 発足10周年を記念し, 「バイオコントロール研究−21世紀への展望」をメインテーマに, 220余名の参加者を得て開催された。午前中は生物防除微生物素材ごとに4つのセッションで構成され, 病害防除における歩みと展望についての総合講演4題, および関連する最新トピックス9題が話題提供された。糸状菌では, 有用株の選抜から商品化へのプロセスの紹介, エンドファイトや菌類dsRNAの利用および誘導低抗性機構について, 細菌では, 蛍光性シュードモナスの実用化, 組換え体の利用, PGPRの生態およびイ手細菌病防除が, また弱毒ウイルスでは, 実用上の諸問題および新規作出法が, さらにIPMにおける生物防除技術の位置付けと微生物殺菌剤の組込みに関して, それぞれ発表があった。 応用生態学的見地から生物防除研究の現状および展望について考察を加えた基調講演をはさんで, 午後は講演者および座長を中心にパネルディスカッションが行われた。活発な討議の中から, 生物防除技術の現場普及における新たな問題も浮き彫りにされ, これらの解決に向けて挑戦すべく, 本会の継続的発展を期する様々な提言を受けて盛会裡に閉会した。(土屋健一) (3) 第9回殺菌剤饒性菌研究会 第9回殺菌剤耐性菌研究会シンポジウムは, 平成11年4月5日, 新潟大学教養校舎で開催され, 141名の参加が得られた。灰色かび病菌のアニリノピリミジン系殺菌剤に対する感受性検定法の統一化に向けて, クミアイ化学工業, アグレボジャパン, ノバルティスアグロの関連各社を代表して高垣真喜一氏が, 次いでFRACのチェアマンであるP.E. Russell氏が, EU (欧州連合) における殺菌剤の登録と酎性菌のリスクアセスメントについて, 話題を提供した。また, 新潟県における病害と耐性菌 (新潟農総研, 原澤良栄氏) , イネもみ枯細菌病菌および褐条病菌の薬剤耐性 (富山農技センター, 守川俊幸氏) と題して, 栽培現場での問題が紹介された。 そして最後に, メラニン生合成阻害剤はなぜ耐性菌を生じないのか?, 倉橋良雄 (日本バイエルアグロケム) , 山口勇 (理研) の両氏から話題提供を受けた。 本シンポジウムの講演要旨集 (1部 2,OOO円) をご希望の方は, 研究会事務局 (農環研殺菌剤動態研, TEL&FAX: 0298-38-8326) までご連絡ください。なお, 次回は平成12年4月5日(水)に岡山大学にて開催される予定である。(石井英夫) 【学会関連各委員からの報告】 1. 日本学術会議報告 平成11年4月21 〜 23日に開催された日本学術会議総会および2月18日と4月20 〜 21日に開催された連合部会と第6部会について簡単に紹介する。なお, 詳細は本会記事を参照していただきたい。4月の総会では各委員会の審議状況が報告された後, 2月の連合部会で示された学術会議の自己改革案について熱心な討議が行われ, 秋の総会までにその原案が作成されることになった。なお, 今年度は日本学術会議の創立50周年に当たるので, それを記念した式典が10月28日に開催される。また日本学術会議50周年史が刊行され現在発売中である。昨年11月に第6部会が中心となって設立された日本アカデミーの主催によって, シンポジウム「21世紀の農学のビジョン」が6月2日(水)の13時30分より日本学術会議講堂において開催される。 また, 6月3日(木)の13時30分より学術会議講堂において, 学術会議第6部と第6部関連登録学協会との連絡会議が開催された。(土崎常男) 2. 日本学術会議微生物研究連絡委員会報告 平成11年3月10日に開催された第4回委員会と関連活動について報告する。1999年8月, オーストラリアで開催予定の国際微生物連合 (IUMS) への3名の代表派遣に, 竹田美文 (現IUMS副会長) , 篠田純男委員 (微研連幹事) を決めたが, 他の一人はMycology関係の参加者の中から人選することとした。また, Bacteriology and Applied Microbiology の Vice President に別府輝彦・日大獣医学部教授を推薦することとしたが, Mycology および Virologyには役員の推薦を見送った。2000年オーストラリアで開催が予定されているアジア微生物連合 (FAMPS) には, 微研連を日本の窓口とし参加することを意志表示し, 年会費は各学協会で分担する案を決めた。 渡辺委員より, 我が国の微生物資源確保・整備体制の構築のための基本的視点, 中核的微生物資源センターの基本方針等に関する基調報告があり, これを土台に議論し, 今後構想案を煮詰めていくこととした。微研連として文部省科学研究費補助金の審査への関わり方について意見交換し調整している。(道家紀志) 3. 日本学術会議植物防疫研究連絡委員会報告 平成11年3月18日に開催された第5回植物防疫研連委員会について簡単に紹介する。なお, 詳細は本会記事を参照していただきたい。横浜植物防疫所の後藤政昭氏から植物防疫の現状というテーマでヒアリングを行った。11年度の国際会議代表派遣として宮田委員 (応動昆) の国際植物保護会議への派遣が認められた。科学研究費の植物防疫研連の1段審査委員の定員は平成12年度より3名から6名に増員されることになり, その各学会への配分が検討された。病理学会2名, 応動昆学会2名, 農薬学会1名, 雑草学会1名の原案が提案されたが決定するに至らず, 改めて各委員の意見を聞き検討することになった。なお最終決定は委員長, 幹事に一任された。 11年度の植物防疫研運主催のシンポジウム「植物保護関連の内分泌攪乱物質の実態」が11月12日(金)午後, 学術会議講堂で開催される。講師は農薬関連の研連委員によって選任中である。(土崎常男) 4. 日本農学会報告 (1) 平成11年度日本農学大会
(2) 平成11年度第2回運當委員会議事要旨
【今後の本学会の活動および関連学会開催予定】 【国際植物病理学会および関連国際会議の案内】 【会員の動静】 【各種出版物案内】 会員の各種出版物
【書評】
【学会事務局コーナー】 【情報提供および投稿のお願い】 編集後記 |