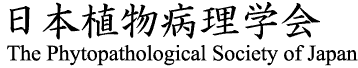【今後の本学会の活動予定】
【今後の関連学会情報】
【今後の関連国際会議情報】
【本学会活動状況 (平成10年6月〜11月) 】
| 1. |
地域部会活動状況
| (1) |
部会開催状況
| ① |
北海道部会
平成10年9月8〜10日, 北海道農業試験場畑作研究センター (芽室町) |
| ② |
東北部会
平成10年10月8〜9日, 磐梯熱海温泉清稜山倶楽部 (福島県郡山市) |
| ③ |
関東部会
平成10年10月2日, 東京大学農学部 (東京都文京区) |
| ④ |
関西部会
平成10年10月16〜17日, 滋賀県立大学 (彦根市) |
| ⑤ |
九州部会
平成10年9月17〜18日, 武田ビル (福岡市博多区) |
|
| (2) |
部会開催報告
| ① |
北海道部会
平成10年度の北海道部会は9月8日 (火) と9日 (水) 10日 (木) の3日間にわたって, 芽室町の北海道農業試験場畑作研究センターで開催された. 参加者は約110名であった. 8日は午後からシンポジウム形式の談話会を行い, 「ジャガイモの病害について」というテーマで5名の方に講演をお願いした.
そうか病・半身萎ちょう病・疫病・ウイルス病・耐病性育種についての講演がなされ, 広く活発な論議がなされた. 夕刻には懇親会が開かれ, なごやかな歓談が2時間続いて終了した. 翌日の9日には9時30分から一般講演が行われた. 分子生物学的基礎研究から防除に関する研究, 新病害の性状など22題の講演が行われ, 活発な論議がなされた.
昼休み後には総会が開催され, 庶務, 会計報告が承認された. また小林喜六部会長が任期を終えるに当たり, 北海道立北見農業試験場長の児玉不二雄氏が次期会長に決定した. 引き続いて一般講演と活発な論議が5時頃まで続いた. 3日目の10日にはエクスカーションが行われた. ジャガイモそうか病防除試験圃場, ダイコンバーティシリウム黒点病発生圃場, 日本甜菜製糖株式会社ビート資料館などを見学し, 午後3時に解散して本年度の部会を成功裡に終了した. (秋野聖之)
|
| ② |
東北部会
平成10年度 (第34回) 東北部会は10月8日 (木) 13時から9日 (金) 13時にかけて福島県郡山市磐梯熱海温泉清稜山倶楽部で開催された. 一般講演ではこれまでで最高の40題 (ウイルス・ウイロイド15題, 細菌病4題, 糸状菌病21題) の発表があり, 122名の参加者のもと熱心な質疑応答が行われた. 特剋講演には三重大学生物資源学部助教授伊藤進一郎氏 (10月1日付けで森林総合研究所東北支所から転任) を迎え, 「養菌性キクイムシの加害による樹木の枯死 −特に日本海側に発生するナラ類の集団枯死被害について−」の題でご講演いただいた.
8日の講演終了後には, 112名の参加を得て研究情報交換会が開かれ原田幸雄部会長の挨拶に続いて山中達名誉会員の音頭による乾杯後, なごやかな交流が続いた. 9日 (8時30分) に開かれた総会では, 会務報告, 学会や懇親会の開催状況, 学会の近況, 収支決算等の報告がなされた. また, 次年度の部会長および部会幹事等を選任, 部会長には秋田県立農業短期大学の松本勤教授を選出し, 次年度開催地は青森県に決定した. (中島敏彦)
|
| ③ |
関東部会
平成10年度関東部会は, 10月2日 (金) 午前9時から東京大学農学部1号館で開催された. 日比忠明部会長の挨拶の後, 46題 (菌類病関係18題, 細菌・ファイトプラズマ病関係16題, ウイルス病関係10題, 線虫病関係2題) の研究成果が, 午前18題, 午後28題に分かれて発表された. 220余名の会員が参加されて活発な討議が行われ, 午後6時頃予定通りに終了した. 講演終了後, 東京大学山上会館において約70名の参加を得て懇親会がもたれ, なごやかなうちに懇親の実を上げた.
最後に, 本年度の部会を無事終了できたのは会員の皆様のご協力の賜物であると深く感謝申し上げる. (日比忠明)
|
| ④ |
関酉部会
平成10年度関西部会は, 10月16日 (金) と17日 (土) の両日にわたって滋賀県立大学交流センターで開催された. 台風10号の接近の影響であいにくの天気ではあったが, 300人近い出席者があり, 一般講演では82題 (ウイルス10題, 細菌12題, 糸状菌60題) の研究成果が2会場に分かれて発表され, 活発な質疑応答でしばしば予定時間を超過していた. 部会初日夕刻には約130名の参加を得て恒例の懇親会が盛大に行われた.
部会開催地委員長但見明俊氏の歓迎挨拶, 地元の名誉会員獅山慈孝氏の音頭による乾杯後, 2時間余にわたりなごやかな歓談が続いて終了した. 役員会は部会初日の10月16日午前10時から滋賀県立大学で開催された. 庶務,会計などの報告が承認された後, 部会会則に基づく選挙により平成11年度部会長に京都府立大学堀野修氏が選出されたことの報告があり, 了承された. また平成11年度の部会開催地として八丁堀シャンテ (広島市) を, 同開催地委員長として半川義行氏が選出され, さらに部会幹事として久保康之氏が, 開催地幹事として奥尚氏がそれぞれ推薦された.
これらの案件は16日午後の総会において提案され, 承認された. (古澤巖)
|
| ⑤ |
九州部会
平成10年度九州部会は, 9月17日 (木) と18日 (金) の2日間, 九州農業研究会との共催により開催された. 17日9時からの講演会への参加者は約140名であり, 29題の発表演題のうち, 糸状菌病13題, ウイルス病11題, 細菌病3題, ウイロイド・マイコ病2題であった. 部会は本大会と異なり, 一会場のみの講演会を設定できるので, 参加者が各種の病原体についての講演を聞くことができることが, 最大のメリットであろう. 大学および県試験研究機関から, 先端技術を用いた試験研究や診断技術についての発表があり, 現場対応に新技術を活用するとの意気込みが感じられた.
18日には, 本部会の企画により実施しているシンポジウムの第23回目を開催した. 話題提供として, イネもみ枯細菌病の病徴発現機構に関する研究 (鹿児島川辺農改普所, 飯山和弘氏) , 日本に発生するジェミニウイルスについて (九州農試, 大貫正俊氏) ならびにナスすすかび病の生態と防除 (佐賀農業セ, 山口純一郎氏) の3題について発表があり, 活発な論議が行われた. なお, 17日18時から, 恒例の応用動物昆虫学会九州支部会会員との合同懇親会が開催されて, これまた盛会であった. (佐古宣道)
|
|
|
| 2. |
研究会開催報告
| (1) |
平成10年度植物感染生理談話会
平成10年度植物感染生理談話会は125名の参加を得て, 平成10年7月16日 (木), 17日 (金) および18日 (土) の3日間にわたり, 神戸市灘区六甲台町の神戸大学滝川記念国際交流会館で開催された. 今回のテーマは植物と病原体の情報応答機構 (Mechanisms of Signal Transduction in Plant-Microbe Interactions) とした.
初日午後からは動物細胞におけるストレスによる情報伝達関連酵素の活性化機構およびRNA結合蛋白質による神経細胞分化誘導機構について神戸大学バイオシグナルセンターおよび同理学部から特別講演を願い, 引き続いて, ウイルス病から「ウイルスゲノムの変異と環境適応」「ササゲにおけるCMV低抗性の分子機構」「N遺伝子が単離されてからのTMV研究」の3題, 2日目は細菌病および土壌微生物の話題から, 「生物発光株とトランスポゾン変異株を用いたRalstonia solanacearumの病原性解析」「植物病原細菌のエリシター生産・分泌関運遺伝子について」「マメ科植物における共生窒素固定根粒形成の分子機構」「植物生育促進菌類による低抗性誘導とその機構」および糸状菌病から「細胞骨格による植物の低抗性発現機構」,「植物の病原体認識とシグナル伝達−細胞壁 (アポプラスト) から核へのシグナル伝達」「ジャガイモ塊茎における防御遺伝子発現とそのシグナル伝達」「タバコ培養細胞におけるエリシターによる細胞死誘導機構」の7題, 3日目も引き続いて糸状菌病から「エンバクにおける抵抗性発現とアポトーシス」
「植物の抵抗性と防御応答に関する伝子発現」の1題の講演が行われた. 最後に総合討論を行い, 植物と各種病原体との相互認識と情報伝達の分子機構について活発な討論が行われ, この分野の現状と今後の問題点の理解を深めることができた. また, レセプションおよび明石大橋ナイトクルージングの懇親会を通じて有意義な学術交流の機会も持った. 運営は主として, 神戸大学農学部植物病理学研究室のスタッフと学生諸君で行った.
ご参加いただいた方々に記して感謝の意を表したい. 平成11年度の植物感染生理談話会は九州大学の高浪洋一氏にお世話いただき九州地区で開催されることとなった. 本談話会の講演集 (1部 2,500円) をご希望の方は, 談話会事務局 (神戸大学農学部内, Fax 078-803-0999) までご連絡下さい. (眞山滋志)
|
| (2) |
第19回土壌伝染病談話会
第19回土壌伝染病談話会は「21世紀における土壌伝染病研究のさらなる発展をめざして」というテーマを掲げ, 平成10年10月21日 (水) と22日 (木) の両日, 140余名の参加を得て東北大学医学部艮陵会館で開催された. はじめに, 遺伝子工学技術の利用による土壌病害研究の進展の成果を確認し, 今後この技術の利用がとくに期待される研究分野について展望が示された.
つぎに, 20年前の第9回土壌伝染病談話会で熱心に討論され, 参加者の関心を集めた「発病抑止土壌」の研究について現時点で総括し, 新たな展望を切り開くため5人のエキスパートの方々からの話題提供があった. なお発病抑止要因の特定が残されている病害も多々あり, 境界領域の研究者との共同研究が望まれる. 主要畑作物の土壌病害の発生生態と防除のセクションではエンドファイトによるハクサイ根こぶ病と非病原性軟腐病菌によるハクサイ軟腐病の生物防除, さらに馬鈴薯そうか病プロジェクトチームの成果ならびにアズキの主要3病害の生態と防除の現状が報告された.
最終日のエクスカーションでは有機性排出物の発酵による循環システムとして国の内外で注目を集めているハザカプラントを見学した後, 同社の会議室で1時間にわたり63名の参加者と社長との熱心な話合いがもたれた. 次回は2年後の2000年に熊本で開催される. (菊本敏雄)
|
|
【学会関連各委員からの報告】
| 1. |
日本学術会議報告
平成10年10月28〜29日に開催された総会と, 7月2〜3日および10月27〜28日に開催された第6部会について簡単に紹介する. なお, 詳細は本会記事を参照していただきたい. 総会では, 会則改正等の議題のほか,「新たな研究理念」,「学術研究の方向性」,「総合科学技術会議の緊急設置」,「俯瞰型プロジェクトの発足」について自由討議を行った. 結論を取りまとめるには至らなかったが今後の参考とすることにした.
7月の信州大学繊維学部での第6部会では,「これからの地球環境を考える」というテーマで公開学術講演を行った. 10月の第6部会では, 日本学術会議第6部会員, 農学系の大学長, 学部長等, 農学系の国立試験研究機関の長等の現職および経験者が中心となって構成される「農学の領域において指導的役割を果たし, もって我が国および世界の農学の発展に寄与する」ことを目的とした農学アカデミーの設立が提案され承認された. (土崎常男)
|
| 2. |
日本学術会議微生物研究連絡委員会報告
微生物連絡委員会 (微研連) は三輸谷俊夫委員長, 篠田純男, 鈴木益子, 宮治誠幹事を中心とした合計18名からなる委員会で, 本年度に入って, 5月と11月に委員会を開催し, 主に次のことを審議してきた. 1) 学術会議第17期の活動方針と第6部微生物研連の学術研究領域での課題, 問題点および将来, 2) IUMS (国際微生物連合) への役員推薦や関わり方, 3) IUMSのアジア版のFAMPS (アジア微生物連合) への加盟と参加のあり方, 4) 生物多様性世界戦略下における微生物遺伝子資源を巡るカルチャーコレクションの役割や我が国のあり方, 5) 微研連主催または共催の公開講演会や公開シンポジウムの企画・調整, 等.
IUMSやFAMPSで積極的に活動する役員が求められている. また, 微生物遺伝子源の我が国での戦略的活用のあり方が問われている. (道家紀志)
|
| 3. |
日本学術会議植物防疫研究連絡委員会報告
平成10年9月9日に開催された第3回委員会および11月13日に開催された第4回委員会について簡単に紹介する. なお, 詳細は本会記事を参照していただきたい. 第3回委員会では(株)トーメン・アグロテックの和田哲夫氏から「天敵昆虫利用の現状」について, および第4回委員会では, 国立環境研究所の森田昌俊氏から「内分泌撹乱物質問題の現状と問題点」についてそれぞれヒアリングを行った. また, 11月13日の午後, 植物防疫研究連絡委員会の主催で第4回植物保護・環境シンポジウム「遺伝子組み換えによる作物保護の諸問題」を日本学術会議講堂で開催し, 応用動物昆虫学会, 植物病理学会, 雑草学会および農薬学会の各1名がそれぞれの分野から講演された.
植物病理学会からは東京大学の日比忠明氏が「病害抵抗性遺伝子組み換え作物の現状と問題点」について講演を行った. 参加者約200名と盛会であった. (土崎常男)
|
【第7回国際植物病理学会議の紹介】
| 1. |
概要
第7回国際植物病理学会議 (ICPP98) は, 98年8月9日から16日までの8日間, 英国スコットランドの古都エジンバラにおいて, エジンバラ国際会議センター (EICC) を会場にして開催された. 本会議は, 英国植物病理学会 (BSPP) が国際植物病理学会 (ISPP) の委託を受け, 英国王女の後援の下に主催したもので, 大会会長はイングラム教授が, 組織委員長はスコット博士がつとめた. 参加者 (事前登録者) は約2,300名, うち日本人は約150名であった.
会議は9日の登録手続きとその夜の簡素な歓迎レセプションを振り出しに, 翌10日, アン王女御臨席のアッシャーホールでの開会式と記念講演から本格的に開始された.
会議の全体プログラムは, (1)植物−病原体相互作用, (2)集団生物学・生態学・疫学, (3)現場における植物病理学, (4)地球的展望, (5)新防除技術, の5大テーマで構成され, シンポジウムとポスターセッションの2部門に分かれて数多くの発表があった. シンポジウムでは, 上記の各テーマごとに6〜14のサブテーマ, 合計47のサブテーマが組まれ, 各サブテーマごとに5〜7課題, 全体で約300課題の講演発表があった. シンポジウムは毎日午前8時半から午後5時半までで, 午前10時と午後3時のティータイムには各30分, 昼食時間には2時間をあてた比較的余裕のあるタイムスケジュールであった.
一方, ポスターセッションでは, 各ポスターが上記の区分に則りながら全体で15のグループに分けられ, 会期の前半と後半で交代して2日半ずつ展示されたが, 合計約1500題にも上る発表があった. このほかに任意のテーマによるイブニングミーティング (午後6時半〜8時45分) が35本あり, さらに, 32の企業・団体の展示も行われた. 主会場となったEICCはエジンバラ市の中心部に位置する地下1階地上3階建の円形で会議機能に徹した現代建築で, 会期中は全室がフル稼働の状況であった. EICCと宿泊施設間の輸送バスも連日運行された. ポスターはEICCに隣接した特設テント会場とシェラトングランドホテル内の会場との2か所に展示されたが, 発表数が多いためかなりの密集状態であった.
5年ごとに行われるこうした大規模な学会の性格上, 各シンポジウムでの冒頭の基調講演は過去5年間の研究の総括という内容が大多数であり, また,シンポジウムにトピックスとして拾われた課題もすでにひとつの仕事としてまとまったものが大部分であったため, これまでの知識の復習や研究動向の整理には役立ってもホットな話題という点ではややもの足りないきらいがあった. その点,ポスターは玉石混交ながら, かなりホットな研究発表も含まれていたように思われる. ただし, こちらはなにしろ数が多いため, シンポジウムの合間を縫ってポスター会場に駆けつけても, 迷路のどこに目的とするポスターがあるのか, そこにたどり着くまでにいい加減くたびれてしまい, ましてその発表者に直接会って議論できればそれは僥倖であるといってもよい状況であった.
各専門分野ごとのトピックスに関してはそれぞれご担当のレポーターのご報告をご覧いただくこととして, 全体的な傾向として, 基礎研究では植物−病原体相互作用に関する分子生物学的研究が, 防除研究ではバイオコントロールや病害低抗性トランスジェニック植物の開発研究が, 世界的にますます盛況をきわめているという印象であった. なお, これらの研究分野も含めて, 日本の研究は十分世界に比肩し得るレベルにあり, 優れたポスター発表課題も多かったにもかかわらず, 今回のシンポジウムの招待講演者としては日本の研究者は数人に限られ, 圧倒的多数が欧米の研究者で占められていた点はいささか残念であった. これは言語の問題や今回の会議プログラムが英国主導でオーガナイズされたことによると思われるが, 今回, 本会議に参加した大勢の日本の若手研究者が, この経験を生かして, 次回の会議の場ではさらに大いに活躍して下さることを期待したい.
さて, こうして会議は最終日を迎え, 14日の閉会式において, 次回第8回の会議が2003年2月2〜8日にニュージーランドのクライストチャーチで開催されるとの紹介があり, バグパイプの演奏とともにISPP旗がニュージーランド代表に手渡された. 今回の会議の成果を礎に, 新世紀にかけての次の5年間で世界ならびに日本の植物病理学がどのような発展を遂げるのか, 楽しみなことである. その夜は, スコットランドの酒と料理と踊りを楽しむフェアウェルパーティーで盛り上がり, 午後11時に無事閉会に至った. 翌15日にはスコットランド王立植物園やスコットランド作物研究所などの研究機関を見学する数コースのサイエンティフィックヴィジット, 17〜19日には樹病学関係など数コースのポストコングレスツアーがそれぞれ実施された. 会期中の天候は, この地方特有で変わりやすかったが, ほぼ穏やかで冷涼な日が続き, 会議の合間にはエジンバラ城を訪ねる人々の姿が目立った.
なお, 会期中に開かれたISPPの評議員会ではハミルトン会長, ヴァーマ事務局長, シェファード会計長らによるこれまでの活動報告に引き続き, 一部規約の改正や広報活動等に関して若干の議論があった. また, 同じく会期中に開かれたアジア植物病理学者の集いでは, 中国からアジア植物病理学会 (ASPP) の結成と2000年北京における第1回アジア植物病理学会議開催の提案がなされたが, この件については各国が自国の学会に持ち帰ってその対応を協議することとなった.
今回の国際会議では, その事前登録等に際して英国の会議事務委託業者の不手際が多かったが, 本会議自体は全体にきわめて良く組織され, 運営もほぼスムーズで, 膨大なポスターセッションを特設テントの設営で対応した点など随所に事務局の苦心の跡が窺えた. また, ホームページの開設や電話帳3冊分にも相当する分厚いアブストラクト集のCD-ROM化など電子情報化時代に対応した新しい試みもいくつかあって好評であった. 10年前, 日本でのこの会議 (第5回国際植物病理学会議) の開催にあたってその準備のために多くの会員の方々が数年にわたって大変な苦労を重ねられたことを思い起こし, 今回の英国植物病理学会の非常なご尽力に対して深い感謝の意を表したい. (日比忠明)
|
| 2. |
菌類病(病原性・病害におけるシグナル伝達を中心に)
最近の国際的な学会の特徴は発表者の皆さんがup-to-dateな研究結果を公表せず,論文が発表されてはじめて発表する傾向にあるので, 今回の7th ICPPもあまり期待していなかったが, 予想に反し, かなりup-to-dateな発表の連続で興奮を隠し切れなかった.
菌類病と植物の低抗性遺伝子, さらには防御応答遺伝子の発現制御に関する発表の全般的な印象としては, ここ1 〜 2年のうちに随分研究が進んでいるなと痛感した. しかし, 宿主特異的毒素やサプレッサーに関する口頭研究発表がほとんど無かったのは残念であった. また, 国際学会であるゆえ, アフリカ, 南米, 東南アジアなどの発展途上国からの参加者にも発表の機会を提供すべきであったのだが, 配慮が行き届いていないのが惜しまれる.
第1日目は“Gene-for-gene interaction: molecular structures and functions"と題してバハニンゲン農科大学のdeWit教授のopening remarksに始まり, 菌類病のgene-for-gene仮説を裏付ける低抗性遺伝子 (Rgene) と非病原性遺伝子(avr)に関してまとめがあった. トマト葉かび病菌(Cladosprium fulvum)のavr9に対応するトマトの低抗性遺伝子Cf9のcDNAをクローニングし, Arabidopsisに形質転換したところ, ナス科櫃物およびその他の植物種の原形質膜との結合が見られたが,Arabidopsisでは見られなかった.
このことはavr9はCF9タンパクに結合しないか結合が非常に弱いものと思われる. この結合の強度はHR誘導能と深い関係にある.
また, Barbara Valentはイネいもち病菌(Magnaporthe grisen)のAVR2-YAMOはヤシロモチの低抗遺伝子Pi-taに対して古典的なgene-for-gene仮説に準ずる反応を示すこと, またAVR2-YAMOを病原性いもち病菌に導入するとPi-taを保持したヤシロモチは過敏感細胞死を誘導することを発表した. さらに, AVR2=YAMOは中性26kDaタンパク質 (Zn-metolloprotease)をコードしていることを明らかにした.
ドイツ, マックスプランクのKmggeらのグループのクローニングしたオオムギ雲形病菌のNip1 (オオムギ低抗性遺伝子) はオオムギに対する病原性を発揮する場合もあり, H+-ATPaseを活性化する. また, 同様の興味深い発見は一部の細菌のavr遺伝子産物はハーピン等と同様に病原性因子として働く場合もある.
オーストラリアのEllisのグループはアマさび病低抗性遺伝子であるL geneの13種類の本遺伝子産物は核結合部位 (nucleotide-binding site) にロイシンに富んだ繰り返し配列 (NBS-LRR) をもち, 13の抵抗性遺伝子はallelic alternative (対立遺伝子のバリアント) であること, また, L1とL8はLRRの領域を欠いており, またL2はLRR領域がduplicateされていることを報告した. さらに, 低抗性の抑制遺伝子も同定され, L10抵抗性遺伝子に対してSnL10が見つかり, L10のN−末端側の5アミノ酸部分に欠損変異が起こっていた. すなわち,
抑制の原因は正常なLlOとリガンドを形成する際の競合, あるいは結合阻害かもしれない.
これは, 特に130アミノ酸のうち6ヵ所のhypervariable領域に見つかっている. また,
宿主特異性はLRRの構造とTIR領域 (Toll & Interleukin receptor に対するホモロジー)
が関与しているらしいことが提案された.
一方, ジョン・イネス研究所のジョナサン・ジョーンズのグループはCf-9の低抗性遺伝子の構造を明らかにし, (1) まず, Cf-9ホモログは少なくとも11個存在すること, (2) LRRのvariantはLXXLXLXXに見られるβ−鎖/β−ターン領域に見られること, すなわち, 欠損とduplicationが起こっていることを明らかにした.
同じく, ジョン・イネス研究所のSchulze-Lefertのグループはオオムギのうどんこ病低抗性に関与する遺伝子をmap-based cloning法でクローニングし, そのうちMlo遺伝子は533アミノ酸をコードし, 7つのtrans-membraneドメインをもつ, おそらくavr産物のレセプターをコードしているのではないかと考えた. 18種類のMlo homologタンパク質が存在し, お互い構造的に類似している. また, Ror7変異体 (ror) はMloを介した細胞死をblockすること, Rar1 (novel zuic finger, ring-domain) 変異体もMloによる細胞死を抑制することから, rar1遺伝子は細胞死のpositive regulatorであろうと推測されている. また逆に, HR細胞死のsuppressorとしてecd1がクローニングされた模様だが, その構造解析はこれからの課題である.
UC Davis のBrett Tylorはエリシチンの結合タンパク質をクローニングし, LRRを含む (ただし, 一般の抵抗性遺伝子のLRRとは構造的に異なる) N-末端にNBSが見出される, ユニークなレセプターであろうと考えている.
以上, 菌類病の低抗性遺伝子を中心に御紹介したが, SAR (全身低抗性) , 過敏感細胞死に関わる活性酸素種の発表などは余白の関係上省略させていただきたい. (山田哲治)
|
| 3. |
細菌病
今回の国際会議では, 細菌および細菌病としてのまとまったセクションはありませんでした. 5つの大きなテーマにおおよそ従って発表が振り分けられていたため, すべての細菌関係の発表を見たわけではなく, また, 自分の発表や, 自分の興味に従ってのぞいたりディスカッションをしたりしていたため, かなり紹介に偏りがあるかも知れないことをお断りしておきます. また, 多くの日本の研究者のかたのすばらしい発表もありましたが, あえてここでは海外の研究発表にしぼらせていただきました.
いろいろと分散していた発表の中で, シンポジウムの1.5 Gene regulation in plant pathogenic bacteria, 1.7 Behaviour of bacteria on plant surfacesと1.6 Secretion systems and pathogenicity genesの3つだけはまとまって細菌の話題であり, この分野にいかに興味が集中しているかがわかります. いずれも植物と病原細菌がいかに相互作用を行っているかを分子レベルで追求するもので, 多くの興味ある発表がありました. そのなかで, hrp-avr関連遺伝子について, 従来検討されてきた遺伝子群の両側近傍にさらにavrなどを含む病原性関連遺伝子がより長大なクラスターをなしていること, これらの制御が単一のカスケードによるのではなく, 多くの異なった制御機構が複雑に制御しあっていることなどが明らかになってきました. また, hrpなどのtype III分泌システムによって分泌されるタンパクが必ずしもharpinだけではなく, Hrp線毛(hrpA)やさらに複数のタンパクがあり, 中にはhrpWのようにharpinとpectate lyaseの両方のモチーフを持つものがあることが報告され興味深いものがありました.
また, Hrp線毛の役割がくりかえし強調され, 特に感染過程の切片の電子顕微鏡観察でHrp線毛が植物細胞壁を貫通していると思われる像が発表され, しかもこの細菌の付着と繊毛形成が菌体の側面ではなく端で起こるらしいことも示され大変印象に残りました. このようにhrpシステムの上流と下流に向かって研究が大きく進んでいることがわかりますが, 植物からの直接のシグナルとそれを受け取るところがhomoserine lactone類以外にあまりよくわからないことや, type III分泌システムによって分泌されるタンパクがさらにどんな反応を植物の中でおこすのかが, これからの課題になって行くところだと思われました.
この分野で特に手法的に注目されたのがYeast two-hybrid systemを用いたタンパク相互作用の解析と, Transient Agrobacterium assayを用いた弱いavrと植物タンパクの相互作用の検出などで, 多数報告されており, 今後常法となることが予想されました. また, 植物病原細菌でもついにDifferential display-RT-PCRが応用されるに至り, 今後の進展が期待されます. さらに, この分野で人間と植物の共通感染細菌とされるPseudomonas aeruginosaが研究対象となってきたことも注目されました. 一方, Ralstonia solanacearumとアラビドプシスを用いた青枯病低抗性遺伝子の解析も始められているようです.
バイオコントロールの分野では相変わらずPseudomonas fluorescensとBurkholderia cepaciaが多用されていましたが, 少しずつメカニズムの研究が進んできたところと思われます. 抗菌物質を過剰生産するようにした試みがありましたが, 実際にはさほど際だった効果は出ず, むしろ他の要因について, 例えば全身抵抗性を誘導するメカニズムなどの研究も進展しているようです.
同定分類に関しては, 生物多様性や迅速診断などのカテゴリーで扱われていました. この中ではXanthomonas campestrispv. zinniaeがトマトに病原性があるという報告や, Pseudomonas syringaeによるバラの枝枯病の報告, Xanthomonas campestris pv. campestris にレース分化があるという報告などが興味を引きました. さらに分類手法としてはREP-PCRやBOX-PCRやAFLPなどを用いた類別と迅速同定の発表が目につきました.
Xanthomonasの分類については単独のイブニングセッションがあり, ディスカッションができるかと思っていたのですが, 実際にはDNA homology groupがREP・PCRやAFLPなどで区別, 同定できるというアメリカのLacyらのグループの一方的な発表があっただけで, 本質的な討論はないまま終了しました. この結果, 今後ともしばらくの間, いろいろな人たちがそれぞれバラバラの分類体系あるいは学名を採用することになりそうで, 決着はつきそうにありません.
とにかく, 今回の発表では病原性やその他の表現形質を無視したDNAやPCR一本槍の発表が目につき, とてもこれでは現場の二一ズに対応できないのではないかと思ってしまいました.
最後に, 非公式なセッションのなかで, ゲノムプロジェクトについての話題がもちあがりました. 種々の植物病原細菌について全ゲノムのシークエンシングを行うのを世界のいろいろな研究機関が重複のないように分担してはどうかという話で, 今後, 具体化したときには是非日本も参加して推進されることが必要であると感じました. (瀧川雄一)
|
| 4. |
ファイトプラズマ病
ファイトプラズマ関連はポスターセッションに8題のみであったが, 色々なジャンルに分離されていたこともあり, すべての著者から直接話を聞くのは困難であった. また, ファイトプラズマ研究者の主要メンバーが直前にシドニーで開かれた国際マイコプラズマ学会 (IOM) へ出席し, そのうちほんの数名を除いて, 多くがICPPへは参加しなかった模様である. 以下に, 発表の概要を, 簡単に分類して記す (かっこ内はポスター番号) .
診断と検定: ①今となってはなつかしいDienes染色とDAPI染色, そして超薄切片法による診断法を比較したもの (3.3.1). 結論は, Dienes染色が実用的. ②中央アメリカでトウモロコシの重要病害である「Corn Stunt com-plex」はmaize bushy stuntファイトプラズマ, スピロプラズマ(S. kunkelii)とmaize rayado finoウイルスの3者が関与する. PCRとELISAの組み合わせで育種圃場の検定品種を調査した結果, ファイトプラズマとスピロプラズマが3か国ではじめて検出されたほか, 感染率はスピロプラズマが最も高く, ウイルスはやや少ないものの被害が大きくなる可能性がある.
これらは, 従来の病徴診断ではわからなかったことであり, 新しい検定法の普及によって的確に診断することが望ましい (3.3.37).
新病害と分類: ③ニュージーランドのイチゴ, cabbage treeとboysenberryからPCRで検出されたファイトプラズマはアサのyellow leaf病原と同一であった (6.20) . ④トネリコ類とライラックに感染するAsh yellowsの系統間の異同をPCRとモノクローン抗体を用いて調べた結果, リボソーム遺伝子と病原性に多少の変異は認められるものの, 同一分類群に所属することがわかった. 2属のヨコバイの少数個体からファイトプラズマが検出されたが, 媒介種は未確定 (2.2.11) . ⑤タイのサトウキビに発生するwhite leafとgrassy shoot, およびイネ科植物のwhite leafファイトプラズマの相互関係について, リボソーム遺伝子のRFLPなどではサトウキビの2種は同一グループに属し, イネ科植物のものとは別グループを形成する.
既知の媒介者以外のヨコバイからもファイトプラズマが検出され, 媒介者の可能性が示された (2.2.99) . ⑥キマダラヒロヨコバイで媒介される12種の日本産ファイトプラズマ病は, 検定植物への虫媒伝染と16Sリボソーム遺伝子による解析の結果, 同一の病原によって起こることがわかった. 本病原はX-diseaseと近縁である (2.2,24) .
媒介: ⑦キリてんぐ巣病がクサギカメムシで媒介されることが再確認された. さらに, 本病原の16Sリボソーム遺伝子において, 接種源のキリ, 保毒ヨコバイと発病ニチニチソウの3者共に, それぞれ複数のクローンについて, 2種のわずかに変異した配列が認められ, この2種が伝染に含まれていたことが示唆された (3.7.33) .
膜性タンパク質: ⑧ファイトプラズマの培養が未成功であることの理由の一つとして, 植物細胞膜および昆虫細胞膜と病原の外被膜との密接な関係が必須であるという可能性がある. アスターイエローズの1系統について, 抗体を用いて精製したタンパク質の配列に基づいて得たPCR産物中に膜タンパク質の遺伝子と推定されるものを得た (1.5.9) .
結び: 思い起こせば, ちょうど30年前, 1968年の8月にロンドンで開かれた記念すべき第1回ICPPで, 明日山秀文教授が, 前年に日本植物病理学会報に掲載されたばかりのマイコプラズマ様微生物 (MLO) について, 公式には恐らくはじめて国際的な場で講演されて大きな反響を呼び, 会議委員長をつとめられたF.C. Bawden博士はじめ世界中の人々から賞賛されたと聞いている. 筆者としては, いささかの感慨を抱いて参加した会議であったのだが, そんなことを語り合う相手もなく, この分野としては寂しい印象の会議であった.
なお, 本稿を草するにあたり, 項目検索機能のない要旨集とCD-ROMにめげずファイトプラズマの項目を検索しご教示いただいた田中 穣氏に深謝の意を表する. (奥田誠一)
|
| 5. |
ウイルス病
エディンバラの街は築100年以上のビルが多くその外観は渋いうすい茶系で統一され, まさにイギリスの古都と呼ぶにふさわしい落ち着いたたたずまいを見せていた. 大会委員長でエディンバラ王立植物園長のイングラム博士, およびアン王女の開会の辞では, 21世紀なかばには世界の人口が現在の倍の110億人になると予想されるなかで, 食料問題と作物保護の重要性がさかんに強調されていた. この傾向は大会のプログラムに強く現れていて, 5年前の第6回モントリオール大会と比較してまさに植物分子病理学とでも呼びたくなるほど分子レベルでの研究が進みつつあることと合わせて, 21世紀問題と分子レベルの研究が今大会の2本柱のようになっていた. このため病原別セッションが少なくなっていたが, 今後の植物病理学の進むべき方向性がプログラムに示されているように感じられた.
しかしこのためにウイルスの発表があちらこちらの会場に散らばってしまった. ウイルスだけのセッションは「ウイルスの病原性」「ウイルス低抗性のメカニズム」「ウイルスと媒介生物の関係」のわずか3セッションのみで, 他のウイルス関連の発表は他の病原と一緒のセッションの中に紛れ込んでいた. タイトルだけのプログラムが無かったために, 3冊もの重い要旨集を広げてウイルス関連のポスターやシンポジウムでの発表を探し出すのはきわめて大変な作業であった. またメイン会場から遠く離れた2会場のシンポジウムも聞くことができなかった. このため, 以下には重要と感じられた点の印象のみを記したので, 個々のウイルス/ウイロイド関連の発表についてはお近くの参加者から要旨集のCD-ROMを借りて見ていただきたい.
「ウイルスの病原性」では, 宿主植物にウイルスタンパク質がどのように分子レベル/細胞レベルで働いているのか, あるいは植物側の分子レベルでの反応に関する発表が多かった. ますます分子レベルの研究が進み, 特に植物の反応と病徴発現, ウイルスの移行, ウイルスの病原性の解析に目覚ましい進歩が感じられた. この中では, ウイルスRNAが増幅している細胞を識別する方法が目を引いた. 「ウイルスと媒介生物の関係」のシンポジウムは, レビュー的な話題提供であった. 「ウイルス低抗性のメカニズム」において今大会のウイルス関連で最も活発な発表をしていたのは,間違いなくイギリスのBalcombe博士のグループのジーンサイレンシング関連のものであり, ポスターと合わせると相当量の研究であった. ジーンサイレンシングとは過剰に発現したRNAを分解する機構のことで, 植物に自然に備わっている.
このジーンサイレンシングは, ウイルスに対する植物の水平低抗性に関与している. さらに, ジーンサイレンシングを打破するようなウイルス遺伝子, あるいは「recovery」とウイルス間の干渉作用なども注目された.
また遺伝子組み換え植物利用のセッションがあり, ウイルス病害低抗性作物について発表されていた. 話は横道にそれるが, 現地のスーパーでは遺伝子組み換えトマトピューレーの缶詰が売られていた. 遺伝子組み換えトマト缶は29ペンス (約75円) であったのに対し, 通常のトマトから作った一回り小さい缶が39ペンス (約100円) であった. 販売上で遺伝子組み換えトマトの缶が成功しているのかはわからなかったが, きちんと遺伝子組み換えトマトの使用を表示している点は, 日本と大きく異なる点であろう.
最後になるが今大会で最も強く感じたことは, ウイルス感染に対する植物の水平低抗性と垂直抵抗性のメカニズムが, いよいよ分子生物学的レベルで解明されつつあるという点であろう. この調子で研究が進展すると, 5年後の2003年2月にニュージーランドで開催される大会では, 植物ウイルス感染に対する植物側の応答の分子メカニズムの解明 (たとえば局部病斑形成など) は, 相当なレベルまで進展していると思われる. この分野での日本の植物ウイルス研究の遅れが, 植物ウイルスを研究している者として, 身にしみて感じられた. (夏秋知英)
|
【関連国際会議の概要紹介】
【会員の動静】
【国際協力】
【各種出版物案内】
| 1. |
学会関連出版物
| ・ |
『日本植物病理学会会員名簿』平成10年11月日本植物病理学会, 頒価 ¥2,000 (購入申し込みは学会事務局まで) |
|
| 2. |
会員の各種出版物
| (1) |
久能均・白石友紀・高橋壮・露無慎二・眞山滋志: 新編『植物病理学概論』感染と発病; 糸状菌病 (菌類病) ; 細菌病とファイトプラズマ病; ウイルス病とウイロイド病; 線虫病と生理病; 病原性と低抗性; 病気の伝染; 病気の診断; 農薬; 病害の防除; 植物病理学におけるバイオサイエンス, 平成10年3月養賢堂, ¥3,800
|
| (2) |
谷口旭・羽柴輝良監修:『応用生命科学のための生物学入門』生命現象の科学; 細胞の機能; 発生と分化; 植物と動物の生理; 生物と生態系; 進化と系統, 平成10年4月培風館, ¥2,400
|
| (3) |
駒田旦:『野菜の土壌病害−その発生のしくみと防ぎ方』土壌病害とは; 糸状菌 (かび) による病害; 放線菌による病害; 細菌による病害; ウイルスによる病害, 平成10年6月タキイ種苗広報出版部, ¥2,OOO
|
| (4) |
松中昭一:『新農薬学−21世紀農業における農薬の新使命』農薬の定義と命名法ならびに分類; 農薬の製剤と施用方法; 農薬の環境への影響と環境基準; 農薬0 〜 効用; 農薬の作用機構; 農薬の毒性, 残量基準・使用基準ならびに残留の実態; 農薬の選択性と薬害; 生物農薬; 農薬問題に対する社会的対応; 農薬学各論, ソフトサイエンス社, ¥3,O00
|
|
【書評】
| 1. |
渡邊恒雄『植物土壌病害の事典』朝倉書店, 272頁, 1998年7月, ¥12,000
著者である渡邊恒雄氏は高名なW.C. Snyder先生のお弟子さんである. 著者は土壌病原菌の生態を常に念頭に入れ, そのための分類に精通している貴重な学者である. 本書の内容を見ると1980年より多年月にわたり専門雑誌に連載された『植物の土壌病害』が骨子となっており, その一部は1993年既刊の『写真と図解土壌糸状菌』であり, 同書は続いて英訳され, 国内外で高く評価されている.
本書はこれらを含め, あらためて現在までの土壌伝染性植物ウイルス, 細菌, 糸状菌の分類, 生態, 生態的防除に関する国内外の研究成果を整理し, 集大成されたと考える.
本書は第I編とII編, III編に分かれ, 構成されている. 第I編は6章からなる総論である. その内容は, 土壌病害と土壌病原体の生態, 土壌病原体の種類とその病害, 土壌病害の診断, 土壌病原体の決定に関する諸問題, 土壌病原菌の行動と関連する諸因子との生態学的な諸問題, 最後は簡潔に土壌病害研究と分子生物学に触れ, 以上について多くの事例を引用し, 著者の土壌病害に対する見解をまじえ, 解説されている.
特に第2章には, 植物ウイルスを含め, 主な土壌病害についてその病因, 寄主植物名および病名を一覧表に整理し, 特に糸状菌の場合は異名等が併記され, わかりやすい. また, 第5章は第II編各論のうち, 最も重要な土壌病原糸状菌とその病害に関連があり, 12の項目に分け詳述されており, あらかじめ理解しておきたい章である.
本書の7割強を占める第II編は各論であり, 14章から成っている. 第1章は土壌伝染性ウイルス病であり, 線虫媒介, 菌媒介, 媒介者不明に分け, 病害の種類, 病徴, 病原の決定手段・性状などの解説である. 第2章は放線菌を含む土壌伝染性細菌病であり, 病害の種類, 菌の分類・同定, 系統・レース, 検出技術, 土壌中の生存などが解説されている. 第3章から14章までは土壌病原糸状菌とその病害についてであり, 著者の得意とする分野でもある.
第3章アブラナ科根こぶ病とその病原菌, にはじまり, 結びは林木の土壌病害, 第14章Heterobasidion annosumによる根株心腐病であり, 計12属の土壌病原糸状菌とその病害について, (1)特徴と分類・同定, (2)菌の生態, (3)寄主植物への侵入と感染, に大別して丁寧な解説がなされている. 著者は国内外で最も重要なPhytophthora, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia 属菌による4病害に関しては, さらに小項目に分け, 詳細に解説されている.
その内容から結論として, これら病原菌の豊富な分離法, 検出法の研究成果は, より合理的な分類方式の確立や土中におけるこれら病原菌の生態解明に役立ち, ひいては感染能力の解明に連動するものと解釈される. なお国内では古くから研究されている紫紋羽病は, 不完全世代がR. crocorumに属するため, RRhizoctonia属菌の章に僅かに引用されている. このような例は本書の随所に見られ, その数は80属以上にのぼり, さらなる続刊を期待したい.
本書の第III編は, 土壌病害の生態的防除であり, 序論および前述各論の14病害のうち, 10病害 (ならたけ病と根株心腐病は併記) について9章の各論から成っている. 防除法の骨子は, 低抗性品種の利用を含む耕種的防除, 湛水処理や太陽熱・温湯利用などの物理的防除, 弱毒ウイルスや微生物利用による生物防除であり, 多くの事例を取りあげ, 簡潔に解説されている. なお, 本書は, 本文左欄外にキーワードを記載, 末尾に事項索引 (日本語, 外国語別) ・微生物索引の掲載, 豊富な章ごとの文献 (主に外国) および計290枚余の写真・図・表の掲載など, 全編にわたって多大の便宜が図られている.
本書の書評を依頼され, 最初は走り読みした感想を述べるつもりでいたが, 内容が豊富なため, 多少の時間を費やした. つまり, 本書は文字どおり事典なのである. あらためてこの大著を上梓された著者に心からの敬意を表するとともに, 研究者は無論のこと多くの方々に, 必要なときに必要な箇所を活用する事典として座右におかれることをおすすめしたい. (荒木隆男)
|
| 2. |
S.T. コーワン著, L.R. ヒル編, 駒形和男・杉山純多・安藤勝彦・鈴木健一朗・横田明訳:『コーワン微生物分類学事典』学会出版センター, A5判/536頁, ¥8,000
原書は『A Dictionary of Microbial Taxonomy』(Cambridge University Press, Cambridge) である. 著者のコーワン博士 (S.T. Cowan) と博士の死後編集を引き継いだヒル博士 (L.R. Hill) の紹介は巻頭でなされている. 本書が微生物の分類と命名法の分野で独創性が高く1978年に出版後すでに20年も経過したが質量ともにこれを凌駕する成書がないことから翻訳されたとのことである.
もともとは1968年刊のOliverとBoyd著,『A Dictionary of Microbial Taxonomic Usage』(Edinburgh, 訳本は『微生物分類用語事典』として東京大学出版会から1977年刊行) の改訂版を目的としたが, あまりに広範囲の用語 (1550項目) が収集されたために新たな単行本とされた経緯がある. はじめに「微生物の命名規約」,「分類学のための研究材料」,「分類の哲学」,「初期の細菌分類史」が述べられ, 続いて用語解説がなされている.
著者が細菌分類学者のためであろうか内容が細菌中心となり菌類関係の用語の解説が少ないことと, この20年間にめざましい進歩を遂げた分子遺伝学; 分子生物学や生物工学関連の用語に詳しくふれられていない点が問題となるが, 全体的に科学哲学と該博な知識に基づく適切な批評がなされている. 巻末には「細菌命名の動向」,「命名法体系の基礎と菌類命名の動向」,「菌類科名の標準和名」が付録として訳者たちにより補われている.
微生物分類の読む事典として一読をすすめたい. (渡邊恒雄)
|
| 3. |
岸國平編:『日本植物病害大事典』全国農村教育協会, B5判/1276頁, ¥50,000
本書は10年前に発行された『作物病害事典』の増補改訂版的性格をもっている. 旧版は現場にあって病気と向き合う病理の研究者, 技術者にとっては無くてはならない性格のものであった. 私たちの総合研究センターでも背表紙が崩れるほどに使いこんできている. 今回, 10年を経て新しく『日本植物病害大事典』として刊行された. この10年間の植物病理研究の進歩を思えば, 関係者に心待ちにされていた出版である.
旧版では食用作物, 特用作物, 牧草および芝草, 野菜, 草花, 果樹, 鑑賞樹木, 不完全菌類の形態の8部からなっていたが, 今回はそれに, 林木と野生植物が加わり, 不完全菌類の形態が削除され9部構成になっている. 基本的な考え方として旧版同様に巳本で発表されている病気についてはすべてが掲載されている. しかも, そのほとんどがカラー写真で示されている. この本の素晴らしいところはすべての病害を網羅しているということである.
このような本は世界にも見当たらない. 使うほうから言えば, ある植物の病気を見つけたとき, そのほとんどは本書に記述があり, 本書に無いものは新病害の疑いが濃いということである. このことは実際仕事をしていく上では大変重要なことであり, それが今回, 林木と野生植物が加わったことで, さらに充実したと言える.
また今回の新版ではいろいろと細かいところにも気を配って改良がなされている. その1, 2をあげると病名に英名が記載されたこと, 目次のところに色分けで病原がウイルスであるか, 細菌であるか, 糸状菌であるかがすぐわかるようになったことなどである.
ひとつ希望を言わせてもらうならば, 序にも書かれているように, 情報科学の進歩は目覚ましい. すでに多くのカタログ類がCDで配布される時代になっている. また, CABIから病虫害概要 (Crop Protection Compendium) についてテスト版のCDも配布されている状況を見ても, できるだけ早くCD-ROM化をして欲しいと思う. いずれにしても, 本書は手元においてぼろぼろになるまで使いこむ価値のある本であり, 植物病害に関係する人の座右の書となって欲しいと思う. (浅賀宏一)
|
【海外留学印象記】
「世界をリードする研究社会」
私が留学したカリフォルニア大学バークレー校は, アメリカ西海岸の代表都市サンフランシスコのとなり町,
バークレー市に位置します. 私は, Department of Plant & Microbial Biologyに所属するBarbara
J. Baker教授の研究室に留学しました. Baker教授の研究室は既に皆さんもご存じの通り,
1994年に植物ウイルス (タバコモザイクウイルス) の抵抗性遺伝子「N」を世界に先駆けてタバコから単離しました.
Baker研究室では, 教授をはじめとして18人中13人が女性でした. この研究室に限らず,
室員の半数を女性が占めるのは珍しくありません. 日本では女性の職場進出が叫ばれている今日この頃ですが,
アメリカでは多くの女性が既に男性と対等の立場で仕事をしています. 西欧諸国の研究室では,
必ずと言っていいほど各研究室で数人のポスドクが実験しています. ポスドクはその研究室で一旗揚げた後その業績を引っ提げて,
大学, 公官庁さらに民間などへ研究者としての定職を求めます. 求人広告を見ると,
その職での研究従事比率が高ければ高いほど「ポスドクを2年以上経験している人」という応募条件が記載されています. 将来研究者を目指そうとしている人たちには,
ポスドクというポジションは避けて通れない一種の登竜門になっています. Baker研究室のポスドクは,
その出身学問領域がバラバラです. ある人は酵母の遺伝子発現であったり, またある人は動物のホルモンであったりと,
とても日本の研究室では考えられないような状況がそこにあります. 日本の研究者のように一つの学問領域を大学時代から究めようとするのではなく,
若い時代にいくつもの学問領域を自ずと渡り歩いている様子です. それは過去の経歴でもそうです. 大学,
大学院, ポスドクのポジションと次から次に所属を変えていくのがこちらの評価されるスタイルと聞きました. 若いときから色々な組織や学問領域を渡り歩くことによって,
将来を担う研究者の卵に多くの知識と価値観を身につけさせようとしています. 採用する側の組織もその人を通して異分野の考え方を知ることができるというメリットがあるようです.
相互に発展が望めるような社会構造を作り上げています.
世界の自然科学をリードしている西欧諸国では, 一連の研究活動が上記に示した社会構造によって支えられているようです. 日本の科学研究を憂いて平成7年に「科学技術基本法」が制定されたことは喜ばしいことですが, 日本の研究が世界の研究と対等に立ち向かうためには法律だけではなく研究の屋台骨を支える社会構造も併せて変えていかなければならないような気がします. アメリカの小さな研究室から垣間見える, 世界をリードする研究に多くを教えられました. (津田新哉)
【学会事務局コーナー】
編集後記
|