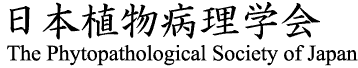| 日本植物病理学会ニュースの発行に寄せて |
日本植物病理学会長 加藤 肇
|
| 「俺は学会をなめていた」. 初めて春の大会に出席した学生達の会話で聞かれた感想の一句である.
表現は無礼で, 活字にするのも揮られるが, 彼らを出席させて良かったと思っている. 学問のありようの一端を理解さすことができればと願ってのことだった.
一般に, 大会, 部会, 談話会などに出てみて初めて学会の存在意義を感じることができるのではないか. 気楽に酒を酌み交わす先生も, 学会で見ると違って見えようというものだ。
学会誌の重要性は論を待たないが, これだけでは学会を身近に感じられない人も多いと思う. 学会活動の多面性については, 長年学会と付き合って来られた方々でも,
不明確な点が多いと思う.
学会員の多くが国公立機関, 民間・法人研究機関や普及機関などに属しているにもかかわらず, 評議員は大学関係者が多いという伝統的アンバランスも影響しているのではないか.
少しでも会員間の風通しを良くしようとの願いから, 今回ニュースを発行 (試行) することになった. Eメールの時代に, いささか遅きに失した感もあり,
方法についても今後検討が必要だろう. いずれにしても, 編集者に人を得なければ不可能. 幸い, 前会長土崎氏がお引き受け下さった. 処女航海も順風を得たと言ってよかろう.
学会員のために発行するのであるから, 生かすも殺すも皆様の関心次第である. 学会はボランティアの幾許かの犠牲で成り立っている. 自らもその一翼を担うつもりで,
身近の関連情報を気軽にお寄せいただきたい. |
|
ニュース発行に至る経緯と今後の予定
平成4年度日本植物病理学会の浅田泰次会長は, 学会と会員の間の連絡を密にしたいと, ニュースの発行を幹事会に提案された. これを受けて幹事会は評議員に対し,
ニュースの発行の是非を4年 ~ 5年度にアンケート調査した. その結果, 平成5年度の評議員会で平成6年度より2年間のニュースの発行の試行が決定された.
発行は年2回とし, 数頁程度を学会報の1号と4号に色刷りで入れる方針である. なお, 平成8年度以降のニュースの発行については, 平成7年に改めて評議員の意見
を聞き決定する予定である。
|
|
|
ニュースの編集方針と編集委員会
| (I)編集方針 |
|
(1)学会報本会記事よりニュースヘ移行する記事 |
|
|
1)国内外の関連学会の学会, シンポジウムの開催案内
2)出版物の案内-防疫協会, 会員の病理関連出版物の案内
3)寄贈図書の案内 |
|
(2)本会記事と重複して掲載する記事 |
|
|
1)学会主催の部会, 談話会, 研究会の開催案内と開催報告
2)学会の出版物 (名簿, 病名目録, 総目次など) |
|
(3)新たな記事 |
|
|
1)学会事務局の紹介-幹事及び事務員の氏名及び異動など
2)学会各委員会の連絡事項 |
|
|
|
a)編集委員会 (編集状況, お知らせなど)
b)病名委員会 (編集状況, お知らせなど)
c)その他の委員会 |
|
|
3)会員の動静 (会員の入会, 脱退, 死亡は本会記事で) |
|
|
|
a)農水省研究機関および県農試の病理関連の室長以上の昇任及び人事異動
b)大学の植物病理関連研究室の助教授以上の昇任及び人事異動
c)大学, 農水省などの新規採用
d)大学博士課程の学位取得卒業者 (課程以外の論文博士は除く)
e)会員の海外への長期出張 (10ヵ月以上)
f)外国人研究員の日本国内滞在日程 (6ヵ月以上) |
|
|
4)会員の意見(400字以内) |
|
|
|
a)学会運営への注文や学会主催の講演会・出版物に対する感想など (自由投稿, 場合により依頼)
b)紙面の制限などもあり採択の有無は編集委員会で決める |
|
|
5)学会主催の記念行事の紹介 (例:80周年記念事業)
6)国際植物病理学会, 国際植物保護会議などの動向
7)植物病理学関連の国際会議報告
8)本会会員の関連学会における受賞
9)外国研究機関訪問記あるいは留学体験記 (800字以内, 依頼あるいは投稿)
10)大学, 農林水産省の海外協カプロジェクトの紹介
|
| (II)編集委員会 |
|
委員長:ボランティア, 委員:学会庶務幹事長, 学会庶務幹事 (1名) , ボランティア若干名で構成し, ボランティアの任期は2年,
2期まで可.
平成6年 ~ 7年度の編集委員会
委員長:土崎常男 (ボランティア)
委員:八重樫博志 (学会庶務幹事長) , 門田育生 (学会庶務幹事) , 日比忠明 (ボランティア)
|
|
|
| 学会事務局紹介
平成6年度の定期総会において新旧幹事の交替が行われ, 本年度は八重樫博志氏 (庶務幹事長) , 門田育生氏, 加納健氏, 竹内妙子氏
(庶務幹事) , 柏崎哲氏 (会計幹事) の5名が担当することとなりました. ご支援ご協力をお願い致します. 平成4年度と5年度の2年間幹事を担当された日比忠明氏
(庶務幹事長) , 土屋健一氏 (庶務幹事) , 夏秋啓子氏 (庶務・会計幹事) のお三方には大変ご苦労さまでした. また, 学会事務局の事務員は鈴木弥江子氏と鶴見典子氏のお二方で,
そのほか前野敦子氏にパートとしてお手伝い頂いております. これまでどおり3人で日本農薬学会, 日本応用動物昆虫学会および日本植物病理学会の事務全般を担当して頂いております.
いずれも3学会のことに精通した方々ですので, 何なりとお問合せ下さい.
|
|
平成6年度前期学会活動状況
1.地域部会 |
|
1)開催状況 |
|
2)開催報告
九州部会:
平成6年度日本植物病理学会九州部会は, 九州農業研究会との共催で, 9月21日(水), 長崎県諌早市にある諌早市民センターで行われた. 講演題数は24題で, 終日熱心な発表と討論が行われた.
翌日, 22日(木)には第19回目を迎えた恒例の九州部会シンポジウムが開催され, ウイルス関連2題と糸状菌関連2題が発表され正午盛会裏に終了した.
なお, 初日の午後に行われた幹事会において, 次期部会長に鹿児島大学の荒井啓氏が選出されたほか, 宮崎県が次回の開催地に選ばれた.
一方, 九州地区で担当することが既に決定している平成8年度の全国大会は佐賀大学にお願いすることで了承が得られた. (松山宣明)
関東部会:
関東部会は千葉大学園芸学部平野和彌部会長の任期満了を受け, 平成6 ~ 7年度は宇都宮大学農学部奥田誠一部会長の下で運営されることとなった. 前回 (昭和55 ~ 56年度, 若井田正義部会長) お引き受けして以来12年ぶりとなる.
本年度部会は, 平成6年9月22日宇都宮大学大学会館で開催された. 会館は昨年11月に竣工したばかりで, そのホールは自動繰出し式の階段座席が設置され, 補助椅子と合わせ280人余りを収容できる.
今回は, 例年と同程度の49題の講演があり, 時間が窮屈なのは相変わらずであったが, 9時30分から開始し, わずか40分の昼休みをはさんで休憩なしで進行し, 全講演を終えたのは18時15分であった.
参加者総数は約220名を数えた. 昼休みには, 飯田格名誉会員, 若井田正義永年会員をお迎えして役員会が開かれたが, とくに審議すべき事項は提示されなかった.
夕刻には, 生協食堂で, 約70名の参加を得て懇親会が開かれた. まず若井田名誉教授から歓迎の挨拶があり, 次に, 部会長から, 折しも来学中の中国浙江農業大学 (杭州市) 張柄欣教授 (植物病理学・国際交流所所長) が紹介され, 寺中理明名誉教授の音頭で乾杯後開宴した.
なごやかな歓談が8時近くまで続いて終了した. (奥田誠一)
東北部会:
平成6年度東北部会は創立30周年の節目の年に当たるため, 記念大会として10月6日(木)と7日(金)山形市遊学館で開催された. 一般講演 (32題) の他に記念事業として記念講演会と記念パーティが開催され, さらに部会創立30周年記念誌「東北地方における作物病害研究の歩みと展望」が刊行された.
記念講演会では, 東北大学名誉教授山中達氏が「東北部会創立当時の頃」, 東北農業試験場斉藤初雄氏が「平成5年イネの大冷害といもち病の発生様相」, 東北大学農学部羽柴輝良氏が「欧米諸国における最近の植物病理学研究事情」の各演題で講演し, 大会参加者 (114名) に深い感銘を与えた.
大会初日の夜に開催された記念パーティには名誉会員, 永年会員, 歴代部会長の諸先生も多数ご出席され盛大に挙行された. また, 記念誌は84名の会員が執筆し, 東北全般, 東北各県の植物病害発生の変遷と現状の紹介, 今後の植物病害研究の展望を主な内容とし, 総頁数が280頁に及ぶものとなった.
部会総会では, 会務報告, 学会・各種談話会の開催状況, 学会の近況, 東北部会の状況, 収支決算等の報告がなされた. その後, 次期部会長に羽柴輝良氏を満場一致で選出し, 新部会幹事, 次期開催地 (秋田県) を承認して本年度の部会は終了した. (富樫二郎)
関西部会:
| (1) |
開催場所:倉敷市芸文館(倉敷市中央1-18-1) |
| (2) |
開催日時:平成6年10月21日(金) |
| (3) |
プログラム:演題数87特別講演 (D. Mills博士オレゴン州立大) |
| (4) |
出席者数:1308名 |
| (5) |
その他:特記すべき事項:演題数が多く, 発表時間を短縮せざるを得なかった. |
| (6) |
地域部会総会および評議員会報告:
10月20日午後3時より役員会を開催し, 庶務・会計報告を承認した. 部会会則に基づく選挙結果から平成7年度部会長に井上成信氏が当選したことについて報告, 了承された. 平成7年度開催地として大阪府立大学を, また, 開催地委員長には一谷多喜郎氏を選出した.
これらに伴い, 部会事務幹事に前田孚憲氏, 開催地幹事に尾崎武司氏が推薦された. これらの案件は総会において報告, 承認された. 関西部会所属学会員数は600余名 (平成6年10月1日現在617名) に達していることから部会を分割することについて約1/3の会員を対象にアンケート調査した結果, 分割反対の意見が多数 (約2/3) を占めたため,
部会の分割は当分の間見合わせることとなった. (大内成志)
|
北海道部会:
北海道部会の研究発表会は11月8日, 札幌市の北方圏センターで約100名が出席して開催された. 講演数は23課題で例年より若干少なかった. 講演の病原別数は, ウイルス5, ウイロイド1, 細菌2, 放線菌5, 糸状菌10課題であった. そのうち新発生病害, ジャガイモそうか病関連の発表がそれぞれ5, 4課題あった.
昼休み後に開催された総会では庶務, 会計報告が承認され, 部会長は北大農学部の木村郁夫教授が退任され, 北海道立中央農試の土屋貞夫病虫部長が新たに選出された. また, 7日にはシンポジウム形式の談話会が『植物病理学と作物育種の接点』というテーマで開かれた. 実際に育種を担当した人を含め若手4名から話題提供をお願いした.
低抗性品種育成にあたって育種からみて病理に望むこと, 病理分野のなすべき役割などについて活発に論議された. なお, 当部会には発足当時から談話会が開催され, 現在までに通算155回となっている. 外国, および道外から著名な先生が札幌に見られたとき講演をお願いしたり, 会員の研究内容の紹介や外国へ留学, 出張したさいの帰国報告会などをその都度開催している.
一昨年11月からは, 国内の大学から4名, 外国から3名の先生による講演会など6回開催した. 昨年7月には札幌市で植物感染生理談話会カ欄催され, 部会としても積極的に協力し, 多くの会員が参加され成功裡に終了した. (島貫忠幸)
|
| 2.談話会, 研究会 |
|
1)開催状況
2)開催報告
感染生理談話会:
本談話会は今年, 30回目の記念すべき年に当たり, 7月20 ~ 22日に札幌市テルメインターナショナルホテルで開催された. 本年のテーマは「植物疾病におけるGene for Gene説の分子的基盤」で, 10講演と3特別講演が行われた.
第1日目, 初めに谷利一氏が基調講演として「感染生理学31年の歩み」を話された. 次いで「病原菌の非病原性および病原性遺伝子について」はまずN.T. Keen氏 (加州大) が「植物病原体の病原性と非病原性遺伝子」について総論的に話され, 次に林長生氏らによる「いもち病菌の非病源性遺伝子のマッピング」, 続いて拓植尚志氏らによる「Alternaria alternaria病原菌の病原性の分子解析」,
最後に奥野哲郎氏による「病原性および非病原性因子としてのブロムモザイクウイルスの外被蛋白質遺伝子」が講演されて, 1日目は終わった. 第2日目 (特別講演) , まず内宮博文氏の「Agrobacterium rhizogenes Riプラスミドのrol遺伝子の分子・細胞学的解析」があり, 次いで竹葉剛氏による「高等植物に広く存在する花芽形成誘導タンパク質」が話され, 最後に桜田教夫氏によるエイズウイルスの生物学」が話された.
すべて植物病理学の関連分野の講演であり非常に興味深く拝聴した. 午後は親睦交流スポーツとしてゴルフとテニスが行われた. 第3日目は「植物の病害低抗性遺伝子」について5講演があった. その内容はイネのいもち病低抗性遺伝子のクローニング (川崎信二氏ら) , トウモロコシのトランスポゾンによるイネいもち病低抗性遺伝子の単離 (島本功氏ら) , イネ縞葉枯病低抗性遺伝子の解析 (早野由里子氏) , Pseudomonas syringae の非病原性遺伝子に対するダイズ抵抗性遺伝子のクローニング (竹内洋二氏ら) およびトマトの根コブ線虫抵抗性遺伝子のクローニング (高木正道氏ら) であった.
以上3日間の出席者は約200名で盛会裡に閉幕した. 来年度は静岡大 (代表者 露無慎二教授) で計画されることが決定され, 益々の発展が期待される. (木村郁夫)
バイオコントロール研究会:
バイオコントロール研究会は, 脇本哲先生の提唱により今後研究推進を図るべき部門である病害の生物防除をめざして1989年に日本植物病理学会の談話会の一つとして設立された. 本研究会は隔年開催を原則とし, 第4回研究会 (1994年) は平成6年度日本植物病理学会大会の後, 農林研究団地筑波事務所農林ホール (つくば市) において246名の参加者を得て開催された.
今年の主テーマは, 「微生物農薬の実用化をめぐる諸問題」として, 1)微生物農薬開発の現状 (セントラル硝子・高原, 野菜・茶業試験場・築尾, トモノアグリカ・伴野, 農環研・松本, 蚕昆研・佐藤) , 2)生物防除利用微生物の効能とリスク (生物研・土屋, 国立衛生試・三瀬) , 3)カレント・トピックスとして-雑草防除のための微生物農薬開発の現状 (三井東圧化学・郷原, JT・山田) -の3サブテーマを設け, それぞれホットな話題が紹介された.
今回の研究会の主旨は, これまでに得られた多くの生物防除に関する研究成果を具体的な微生物農薬として利用していく場合に何が問題で, どこを解決しなければならないか, このためにはどのような研究が要請されているかを先進企業における具体例を交えて論議することにあった. 農林水産省においては微生物農薬のガイドラインが検討され, 環境庁においても微生物農薬の動態を検討しようとしている今, 研究会の主旨が理解され今後の発展につながることを願っている. (鈴井孝仁)
第17回土壌伝染病談話会:
日本植物病理学会第17回土壌伝染病談話会は全国から215名の参加者を迎え, 平成6年11月10 ~ 11日の日程で, 大阪府堺市の大阪府立大学で開催された. 民間からの参加者が約半数にのぼり, この分野への民間企業の関心の高さがうかがえた.
初日の講演会では, 片山新太氏 (名大農) による特別講演「農薬施用による土壌微生物相の変動-非標的微生物への影響を中心として-」, 草刈眞一氏 (大阪農技セ) による「大阪府における土壌伝染病の現状と問題点」のほか, 「生態学的研究から無公害管理へ」と「予防・管理への新しいアプローチ」の2大テーマのもとに, 松尾和敏, 伊達寛敬, 景山幸二, 梅本清作, 寒川喜三郎, 東條元昭, 竹原利明, 玉田哲男, 豊田秀吉, 山田明の各氏から多方面にわたる話題が提供され, 活発な討論が行われた.
翌日の現地検討会では, 泉大津市の「大阪泉大津フラワーセンター」でコンピュータによる花卉せり売りシステムなどを見学したあと, 泉佐野市圃場でキャベツ根こぶ病の有機質資材による防除試験と養液栽培ミニトマトの昆虫による受粉, 天敵による防除試験の状況を視察, 検討した.
今回の談話会の運営委員は, 一谷多喜郎 (委員長) , 大木理, 尾崎武司, 岡田清嗣, 瓦谷光男, 草刈眞一, 田中寛, 東條元昭, 中曽根渡の各氏である. 現地検討会でお世話になった関係各位にもご協力を改めて感謝したい. なお, 次回平成8年度の土壌伝染病談話会は千葉県で開かれることが決まった. また, 講演要旨集 (土壌伝染病談話会レポート第17号) には若干の残部があるので, ご希望の方はご連絡をいただきたい. (一谷多喜郎)
殺菌剤耐性菌研究会:
殺菌剤耐性菌研究会の第4回シンポジウムが4月6日, 茨城県つくば市で開催され, 以下の講演のあと, 活発な質疑応答がなされた.
イネいもち病菌のカスガマイシン, 有機りん剤耐性とその機構
| 1. |
イネいもち病菌の有機りん剤耐性の機構 (宇部興産(株) 上杉康彦氏) |
| 2. |
イネいもち病菌のIBP耐性 (長野果試飯島章彦氏) |
| 3. |
イネいもち病菌のイソプロチオラン感受性と寄生的適応性 (日本農薬(株), 廣岡卓氏・故宮城幸男氏)
ブドウ黒とう病におけるベンズイミダゾール系薬剤耐性菌の出現とその対策 (佐賀果試 田代暢哉氏)
カンキツそうか病菌のベンズイミダゾール耐性とその防除対策 (果樹試興津 家城洋之氏)
フェニルアマイド耐性の現状と対策
| 1. | Experience with Phenylamide Resistance and Successful Countermeasures (スイス・チバガイギー社 T.Staub氏) |
| 2. | 日本におけるフェニルアマイド耐性植物病原菌の発生状況 (JA全農中澤靖彦氏) |
|
なお, 講演要旨集に残部があるので, ご希望の方は研究会事務局 (果樹試病1研石井英夫TEL.0298-38-6544) までご連絡いただきたい. (石井英夫)
|
|
|
| 平成7年度学会活動および関連学会の開催予定 |
|
| 創立80月年記念事業の進捗状況 |
編集委員長:岸國平氏, 同副委員長:日野稔彦氏, 同幹事長:稲葉忠興氏を中心として編集が進められている. 各分野の多くの学会員が分担執筆し, 創立80周年記念事業にふさわしい内容豊富な事典が,
7年春に養賢堂から発売される予定である. |
|
学会関連の各委員からの報告
日本学術会議関連:
第16期日本学術会議会員として, 日本農薬学会, 日本応用動物昆虫学会, 日本植物病理学会3学会の推薦で松中昭一氏 (関西大) と三橋淳氏 (東京農工大) が, また, 微生物学関連学会の推薦で三輪谷俊夫氏 (岡山県立大) がそれぞれ選出された.
|
|
| 国際植物病理学会および植物病理学関連国際会議の報告と案内 |
|
| 会員の動静 (H.6.1 ~ 6.10) |
|
各種出版物案内
(1)学会出版物
| ・ | 日本植物病理学会会員名簿 平成6年11月, 価格2,000円 |
| ・ | 日本有用植物病名目録第2巻 (野菜および草花)
第3版, 平成5年12月, 価格4,000円
残部がありますので学会事務局へお申込み下さい.
|
| ・ | 日本植物病理学会報総目次
第21 ~ 第50巻 (1956 ~ 1984) , 平成5年9月, 価格2,700円
残部がありますので学会事務局へお申込み下さい.
|
(2)会員の出版物
| ・ |
江原淑夫, 生越明, 土崎常男, 道家紀志, 古澤巌, 脇本哲著:総説植物病理学, 養賢堂, pp.457.1994, \6,695. |
| ・ |
宍戸孝ら編:農薬科学用語辞典, 日本植物防疫協会, pp.374.1994, \7,500. |
| ・ |
大木理著:植物と病気, 東京化学同人, pp.201.1994, \1,300. |
| ・ |
Kohmoto, K. and Yoder, O.C. eds.:Host-specific toxin: Biosynthesis, receptor and molecular biology, Tottori Univ., pp. 313. 1994.
(残部僅少:お問合せはFaxで直接下記へ
FAX.0857-31-5347鳥取大学農学部植物病理学研究室内 鳥取HSTシンポジウム事務担当)
|
| ・ |
Watanabe, T.: Pictorial atlas of soil and seed fungi, Lewis publishers, pp. 411, 1994. |
| ・ |
江塚昭典, 安藤康雄著:チャの病害, 日本植物防疫協会, pp. 440, 1994, \6,500. |
|
|
会員の意見
|
| (1) |
学会ニュースの発行を喜ぶ
心待ちにしていたニュースの発行をお慶び申し上げます. 年に1回定期総会が開かれますが, 出席者は学会員の3割にも満たず, 学会報に載る学会記事もどの位の人が読んでいるかわかりません. 学会を運営する役員の仕事の中身についても多くの学会員は知らないと思います.
ニュースにこの隙間を埋め学会と学会員を結ぶ役割を期待するものです.
そこで, 2, 3注文を.
| ① | 最初は記事が多いでしょうが, あまり欲張らず, 長続きさせることが重要. |
| ② | 学会役員の活動状況を「編集後記」などの形で載せてはいかが. |
| ③ | 海外情報は勿論, 在日外国人の声なども載せてはどうか. |
| ④ | 近い将来ニュースを別冊にし, それだけを購入する会員制度を作れば, 会員の裾野が広がると思います. |
|
|
(果樹種苗協会 山口 昭)
|
| (2) |
本年3月までの2年間, 学会幹事としてお手伝いさせて頂く機会に恵まれた. 正直なところ, それまでの私は, 学会の運営についてはほとんど意識したことがなかった.
しかし, 会計幹事になってみれば, 会費納入の状況が大層気になる. 各会員の元へ直接集金に伺いたくなるほど!であった. また, 普段より多くの人に出会い, 広い範囲の研究に関心を持つようにもなった.
特に, よりインパクトのある学会報を目指した議論を通して, いろいろな意見に接した事が印象に残っている. また, ファックスなどの機器の活用が進み, 思ったほどは時間を取られなかったのも良かった.
私たちは普段, あまり乗り気でない仕事を雑用という一言で片付けてしまう. 幹事役も雑用と言えば雑用なのかもしれない. しかし, 今思うと, 1回位なら経験してみるのも悪くはない, 意外に勉強になる雑用だったようだ.
|
|
| (東京農大 夏秋啓子) |
|
| 情報提供及ぴ投稿のお願い |
|
| 学会事務局コーナー |
|
編集後記
|